前傾姿勢になっていた自らの背筋が、一度大きく跳ねるのを感じた。自分の目に映っていた物の正体を知った途端、驚きと落胆、それプラス恐怖をも同時に受けたのだった。
顔を強張らせながら、瞳孔を大きく開かせる。
「違う……。蓮木さんじゃない……」
石のように固まってしまった千秋の視界の中で、倒れていた人物が僅かに身体を動かした。失っていた意識をたった今取り戻したばかり、といった感じで。その動作は駆動部を錆び付かせてしまった機械を思わせるほどにスローだ。
周囲の地面に赤い染みが微かに広がっている。血で間違い無さそうだった。ぼろぼろに破れたレインコートの裂け目から覗く衣服も、所々が朱に染まっており、いかに“彼女”の身体が大きなダメージを負っているのか窺い知ることが出来る。とはいっても、手足のどこかを骨折するなど、重大な負傷はしていない様子だ。かつての俊敏さは失われているものの、四肢のうち一つを制限された千秋の動作と比べれば、まだまだ十分なほどスムーズといえる。
その人物はのそのそと立ち上がると、千秋の存在に気付いていないのか、しばらく明後日の方向をぼんやり見つめていた。
「白石……さん……」
千秋はやっとの思いで一歩後ろに下がる。
黒ずくめの少女、白石桜(女子十番)は未だ、サブマシンガン一丁をしっかりと握り締めていた。さすがにデイパックは流れに奪われてしまったようだが、とはいえあの濁流の中で、しかも一度気を失いながらも武器を手放さなかったというのは、脅威である。
大粒の水玉をぼたぼたと止めどなく落とす、烏のように真っ黒なレインコート。流れの中で樹の枝にでも何度も引っ掻かれたのか、とくに右半身が広く破れてしまっていた。頭を完全に覆っていたはずのフードの部分も元の形状を失っており、その下の乱れた白髪が、外に飛び出して無造作に跳ねている。
しばらくして、桜はようやく自分以外の人間の気配を感じ取ったか、ゆっくりと千秋の方を振り向いた。しかし表情は全く変わらない。驚いたり、敵意を剥き出しにしたり、そういった感情というものが全く伝わってこなかった。
目を覚ましたばかりで意識がはっきりしていないのか、彼女の目つきは以前にも増して虚ろになっているように思える。顔は千秋の方へと向けつつも、淀んだ目は中空を漂っているかのよう。
見ると、桜はどこかで頭を強く打ってしまったのか、髪の生え際あたりからも血を流していた。そういえば、手足の具合は大丈夫そうなのに、妙に彼女の身体が前後に揺れている。四肢のほうとは違い、頭部のダメージはなかなか深刻なのかもしれない。それなのに彼女は痛がっているような顔も、一瞬たりとも見せたりしない。以前と変わらず、ロボットのようにずっと無表情なままだ。
あまりに表情が変わらなさ過ぎるために、『桜の身体は幾許かのダメージを負っている』、というのは間違いで、実のところ彼女は無傷なのでは無いか、と勘違いすらさせられてしまいそうだった。
人間味が全く感じられない桜に対して、千秋はまた恐怖を覚えてしまう。自分と同じように血の通っている人間であっても、ここまで大きな違いが出てしまうものなのだろうかと、疑問にすら思ってしまった。それほど、白石桜という人間の性質は、千秋がこれまでに築き上げてきた常識から逸脱してしまっていたのだった。
「ひっ……」
ほとんど悲鳴と変わらない声を小さく洩らす。千秋が見ている目の先で、桜が一歩前へと踏み出したのだ。
たかが一歩。しかし千秋はそれだけで、事の重大さを悟った。
桜は未だ目的を見失ってはいない。体に傷を負いながらも歩を進めようとしているのは、何かをしようとする意志がまだ頭の中に残されている証拠。
では彼女はいったい何を目的に、千秋の方へと歩み寄ってこようとしているのだろうか。まさか、手を握って協定を結ぼうなどと思っているわけではあるまい。この場合、濁流に飲まれる以前からの思想が、桜の中でまだ継続されていると考えるのが自然だった。
つまり、彼女は以前と変わらず、千秋たちを殺すことを目的とし続けているに違いない。まさにそれを証明するかのように、小さな手の中に握られていたマシンガンの銃口が、いつの間にか千秋の方へと向けられようとしていた。
飽くなき執念の深さを前にしては、さすがに恐れを抱かずにはいられなかった。
必死の思いでもう一歩後退する。それが今の千秋にできる精一杯の行動。本当は敵に背を向けてでも一目散に逃げ出したい気分だったが、身体がまるで凍結してしまったかのように固まってしまい、思い通りに動かせなかった。殺意という見えない圧力に押さえ付けられて、緊張のあまりか全身の伝達神経が麻痺してしまっていたのだった。
こうなってしまっては、もはや逃げることもままならない。千秋は何もできないまま、迫りつつある終焉を受け入れなければならないような、そんな窮地へと追い込まれていた。
だけど、実際には終わりはなかなか訪れなかった。桜は標的への接近は続けるものの、なかなかマシンガンを撃ってはこなかったのだ。
できるだけ近くに寄って、一発で正確に仕留めようという考えなのだろう。水の流れにデイパックごと銃弾の多くを持っていかれてしまった今、桜には無駄撃ちできるほどの余裕なんて残されていないのだ。
――そう、距離がまだ開いている今、いきなり殺されたりはしない。あとほんの数秒とはいえ時間はある。その間に、なんとか逃れる術を思いつかないと……。
千秋が必死に考えながらもう一歩後退したとき、目の前を何かが横切っていった。ひらひらと空中を漂うそれは、真っ白いモンシロチョウ。肌寒い晩秋を忘れさせるほど優雅に舞い、二人の間に割って入ってくる。
蝶はゆっくりと下降して桜の肩にとまった。「やめて、殺戮はもう繰り返さないで」とでも言っているかのようだった。
桜は頭だけを動かして、自分の肩の方を見る。相変わらず表情に変化が無いので、彼女の考えは読み取れない。
桜は一度銃を下げ、おもむろに肩へと手を伸ばした。そして何を思ったか、そこにいた蝶をいきなり鷲掴みにした。
まさか、と思った瞬間、彼女はそのまま手に力を入れて握り締めた。
千秋は動くほうの手で自らの口元を押さえ、目を見開かせる。
数秒経って桜の掌が開かれると、蝶の潰れた屍骸と白い羽の一部が、地面に吸いつけられるかのように落ちていった。たった今まで元気に羽ばたいていた一つの生命をごみのように、桜は手の中で、いとも簡単に潰してしまったのだ。
その際にも、彼女はまったく表情を動かすことは無かった。生き物を殺すことなんて、息を吸うのと同じくらいに当たり前のことだと思っているかのよう。
寒気がする。命一つを握りつぶすのに眉ひとつ動かさないでいられる人間の存在に、これ以上無いというほどの恐怖を覚えた。
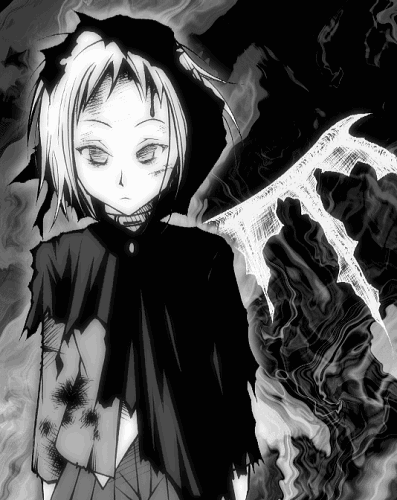
桜の姿が悪魔に見える。背中に生えた翼が、長きに渡る戦いの中で破れてボロボロになってしまっても、息のある者全てを潰し尽くさない限り殺戮をやめない。そんな脅威の存在。
自分よりも小さいはずの少女の身体が、このときは何故かとてつもなく大きくなもののように目に映った。この場を支配する禍々しいオーラが、錯覚、あるいは幻覚を引き起こしたかのようだった。
もはや自我を失う以前の彼女の姿は、微塵も残されていない。
どんなに小さな生き物に対しても優しく接し、いつも無邪気に笑っていた、かつての白石桜という一人の少女は、二年前の火災のときに既に死んでしまっていた。残されたのは中身を失った身体――器のみだった。
今の彼女の状態を見ては、誰もがそう思ってしまうだろう。
「白石さん……」
千秋が悲しげに桜を見つめる。変わり果てた級友の姿をこうして間近で目の当たりにしていると、胸に込みあがってきていた苦しみがさらに酷くなっていった。
ゆっくりと持ち上がりながら揺らめいているマシンガンの狙いが、だんだんと定まっていく。
「ひっ」
銃口が眉間を捉えた途端、千秋は再び声を上げた。同時に、桜の細く白い指先が、トリガーを引き絞るのが見えた。
頭の中が真っ白になった。
【残り 五人】 |
