担当教官たちが妙な動きを始めた。
プログラムの妨害を行ったのは自分達だと、いつばれるか緊張し続けていたためだろうか、すぐ近くで起こっている異変に桂木幸太郎はいち早く気付いていた。
先ほどまでソファーの上に重い腰を下ろして腕を組み続けていた醍醐一郎が、御堂一尉と連れ立って廊下へと出て行ったかと思えば、少しして物凄い形相を浮かべながら部屋に戻ってきた。そして任務に勤しんでいる兵士のうち若い一人を捕まえて、再び廊下へと出ていった。
いったい彼らは何をしようとしているのだろうか。
考えるまでもなかった。醍醐たちはプログラム妨害の犯人を突き止めるべく、ついに動き出したのである。
彼らがどこまで真相に近づいてきているかは分からないが、とりあえずまだ容疑者として特定の人物を搾り出すまでには至っていない様子。しかし、内部の人間の犯行であることくらい、もしかしたらそろそろばれる頃なのかもしれない。
緊張が高まる中、桂木はちらりと横目で、今回の共犯者である木田聡を見た。
彼もまた異変には気付いているらしく、迫り来る恐怖に表情を固めてしまっている。勘が鋭く頭の回転も良いだけに、事の重大さをより鮮明に感じ取ってしまい、落ち着くことが出来なくなっているのだ。精神が揺さぶられてしまっているのか、額から汗が滲み出している。
木田の場合、精神状態が不安定に陥ってしまう原因は、別のところにもう一つあったといえよう。それは湯川利久が語った竹倉学園大火災の真相。事件の関係者であった木田にとっては、ほとんどが以前から知っていた話であったかもしれないが、それにしたって息子の死を思い出させてくる内容の連続には、さすがに堪えたはずだった。
さておき、事態をどうやって乗り切るべきか木田と話し合いたいところだが、現状ではちょっと難しい。醍醐たちが兵士達に目を光らせている今、二人いっぺんに持ち場から離れてしまうと余計怪しまれてしまいそうだ。かといって周囲に他人の目が沢山あるこの部屋の中で、プログラム妨害工作について堂々と話し合っているわけにもいかない。
いったいどうすればいい。
桂木はこれまで、自分達が行った妨害工作はそれなりに安定したものだと思っていた。木田の協力があったおかげで、メインコンピューター内部への侵入も、データ書き換えも、その後のケアも、かなり緻密かつ正確に行えたものだったから。しかしどこかで地盤が崩れたか、安定していたはず計画は今、徐々にバランスを失っていきつつある。こうなってしまってはもはや、桂木たちがいくら考えたところで新たに打開策を見出すことは難しかった。
たしかに、思いつきで実行に移した計画に、ずさんな所が無かったとは言い難い。しかし、今回このような窮地に追い込まれてしまったのは、単純に運に見放されてしまったせいであったとも言える。盗聴回路が不能に陥ってしまう原因なんて、スピーカーやマイクの故障、配線内部の切断、などなど他にも数多く考えられるというのに、メインコンピューターのプログラムに書き換えがあったと、醍醐たちはこちらが思っていたよりもずっと早く気がついてしまったのだ。
不運だ。仮に自分達に繋がる痕跡がコンピューター内部のどこかに残されていたとしても、醍醐たちがもたもたと事態の究明に取り組んでいるうちに千秋たちの働きでダムが破壊されれば、プログラム本部は水に浸かってしまって、文字通り証拠は全て洗い流されてしまうはずだったのに。今の状況からすると、千秋たちが計画を実行に移すよりも早く、醍醐たちが犯人を割り出してしまうことだって考えられる。
桂木たちは今まさに最大のピンチを迎えていた。
が、なぁに、心配することは無い。もしもプログラム書き換えが兵士の誰かによって行われたと知られたとしても、醍醐教官たちが犯人に辿り着くことはできないはずだ。
メインコンピューターへの侵入に使ったノートパソコンは、軍が予備としてこの島に持ち込んだ物。桂木個人のものでも、もちろん木田の物でも無い。そして軍が所有しているコンピューターのIDとPASSは、兵士の多くが知っている。電源ボタンにもキーボードにも、どこにも自分達の指紋を残したりはしていないし、犯行時には誰にも姿を見られないよう努めてきた。以上のことから、内部犯説が有力視されることがあるとしても、何十人もの兵士全員に容疑がかかるだけであって、自分達のみが疑われてしまうことはないはずなのだ。
桂木は以前木田が言っていたことを頭の中で反復し、懸命に自らを落ち着かせようとした。
そのとき、部屋の扉が音をたてて開き、醍醐と御堂、そして廊下へと連れて行かれた若い兵士が戻ってきた。
「協力ありがとう。それでは次に、そこの君に来てもらおうか」
若い兵士が元の持ち場に戻るのを見届けると、醍醐はアフロに手を突っ込んで頭をかきながら、次に、書類を運んでいる途中だった中年兵士を呼び寄せた。そして先と同様に、廊下へと出て行って扉を閉める。
彼らは部屋の外で何をしているのだろうか。
桂木は疑問に思いながら、ちらちらと廊下の方へと目を向ける。引き戸の曇りガラスに中年兵士のものと思われるシルエットがくっきりと映し出されていた。なにやら話をしているらしかった。
数分後、中年の兵士は元の仕事へと戻された。代わりに、醍醐はまた別の兵士を連れて廊下へと出て行く。そして数分経ったら戻ってきて、また別の兵士を連れ出して、と、同じような出来事が何度も何度も繰り返された。桂木はその様子をずっと見ていたが、結局何が行われているのか分からずじまいだった。
そして、ついに自分の番が来た。
「角から三つ目のコンピューターの前に座っている君、悪いがちょっと来てくれないか」
気の強そうな兵士を持ち場に返してから、醍醐は桂木を指名してきた。
ドクンと胸が一度大きく高鳴る。
「いったい何の用で?」
「まあ来てくれれば分かる」
桂木は椅子から立ち上がり、手招きする醍醐のほうへと歩き出す。そのとき一瞬木田と視線が合った。「気をつけろよ」と彼の目が訴えかけてきたので、桂木も「大丈夫だ」と力強い目つきで返した。本当のところ、これから何が起こるのか分からず不安でいっぱいだったが、木田を心配させることは全く無意味であったので、無理して強がって見せたのだった。
醍醐たちに変に怪しまれぬよう、平常心を装いつつ部屋の外へと踏み出す。廊下を通る緩やかな風の流れが、肌を優しく撫でてきた。
「何かお話でもあるのでしょうか」
上官二名を前に問いかける桂木。プログラム妨害には一切関わっていないエキストラ的キャラクターを、ごく自然に演じきれた。
「何者かによってプログラムが妨害された一件は、もちろん知っていますよねぇ?」
「ええ。盗聴回路を司るデータが書き換えられていた、と。それが何か?」
「実はですねぇ、私達は初め、外部犯の可能性を第一に考えつつ技術兵数名に調査させていたのですが、ここにきて急に状況が変わってきましてねぇ」
「まさか、内部犯の可能性が濃厚になってきたとでも?」
「そのまさかなんですよ。どうやら今回の妨害は、外部から行われたものではないらしいのです」
やっぱり、と桂木は思った。醍醐たちは既に疑いの眼差しを内部の人間へと向けている。そんな中、兵士一人一人を順に呼び出しているということは……。
「つまりこれから、事情聴取を行う、ということですか」
「察しが良いですね。まさにその通りですよ」
醍醐教官は少し感心した様子で言った。
継続して平常心を装う桂木。しかし、内心はとても落ち着いていられるような状態ではなかった。
事情聴取は非常にまずい。質問に対して何か一つでも間違った解答をしてしまえば、それが決め手となって容疑者から犯人へと格上げされてしまいかねない。そう、いくら機械の中に証拠が残されていなくとも、犯行を行った人間がボロを出してしまったら、全てが無駄になってしまうのだ。
人間は豊かな発想力で自由に物事を考えることが出来る優れた生物であるが、コンピューターのように常に完璧な計算なんて出来ない。突拍子の無い質問に、瞬時に対応できる自信なんて桂木は持っていなかった。
だがここまで追い詰められてしまったら、もうどこかに逃げることは出来ない。覚悟を決めて醍醐と真っ向から対面し、知恵を振り絞りながらなんとか活路を見出すしかなかった。
「分かりました。何でも聞いてください」
左右のポケットに手を突っ込んで、何もかもを全身で受け止めるとでも言わんばかりに直立する。歯ががちがちと音を立てそうになるのを、顎に力を入れて何とか抑えた。
「それでは早速聞かせてもらいましょうか。メインコンピューター内部へ何者かが侵入したと思われる、昨日の午後一時ごろ、君は何処で何をしていましたか?」
午後一時ごろといえば、プログラム本部の管理をしていた兵達が交代して休憩に入り、ちょうど一時間経ったというころ。他の者たちと同様に、桂木も本来なら仮眠室で休息を取っていたはずだった。
「その時間は物置場にいて、ローカルから本部のメインコンピューターへと侵入して、盗聴回路を不能にする作業を行っていました」なんて証言出来るはずの無かった桂木は、すぐに「仮眠室で眠っていました」と、最も無難な答えを返してしまいそうになった。しかし、ギリギリのところで言葉を飲み込んだ。
桂木は気付いたのだ。醍醐の質問は一見すると、単純に回答者のアリバイを調べるためだけのもののように思えるが、実はここに恐るべき罠が潜んでいるのだと。
おそらく醍醐は兵士一人一人のアリバイを聴取すると同時に、証言の食い違いを見つけ出そうとしている。
つまりこういうことだ。
醍醐は同じ質問を何人もの兵士に投げかけているだろうが、大半からは「眠っていました」という言葉が返ってくるはず。しかし中に、「眠れなかった」や「その時間はちょうど出歩いていた」なんて言い出す者が何人かいたっておかしくは無い。
眠っていなかった兵士なら、犯行時刻に誰が何処にいたか、逆に居なかったかを、少しくらいは知っているはず。それをヒントとして頭に残し、さらに別の人物の事情聴取を続ける。すると、偽りの証言をする者が現れた時に矛盾が発生し、怪しい人物が絞られる。そういう寸法だ。
今回の場合、「犯行時刻、仮眠室に桂木の姿は見られなかった」と証言する者がいた場合、桂木が「仮眠室で休息を取っていました」と言ってしまえば矛盾が生じ、容疑者第一候補として桂木が挙がってしまう、というわけだ。
考えた末、桂木はこう答えた。
「初めてのプログラム管理で緊張していたためか眠れず、少し外の空気を吸いに建物から出ていました」
一つの部屋に何十人もが雑魚寝していた仮眠室の中で、桂木がいないことに気付いた者がいたとはあまり考えられないが、生死がかかっている今は一応細心の注意を払って答えておくべきだと考えた。
これなら他人の証言と食い違いが生じることは無いはず。桂木が仮眠室にいなかったと言う者がいたとしても話のつじつまは合うし、半日続いた仕事に疲れきっている他の兵士が、雨が降っている外にわざわざ出ていくことなんてなかっただろうから。
「その時、一人だったか?」
「はい。誰の姿も見ませんでした」
下手に木田と一緒にいたなんて答えないほうが良いと考えた。どうせこの後、事情聴取は木田にも及ぶことになる。そのとき、彼が「外の空気を吸いに桂木と二人で建物から出ていた」なんて、上手く答えてくれるとは考えられなかったので。それに勘が鋭くて頭の回転も良い木田のことだから、醍醐の質問に対しては桂木と同じように、たった一人で仮眠室ではないどこか別のところにいた、と、最も安全だと思われる返答をするに違いなかった。
「なるほどね」
証言に矛盾が見つからなかったためか、醍醐は小さく頷いて、それ以降とくに質問を続けてきたりはしなかった。
「大変参考になりましたよ。協力ありがとう。それではそろそろ元の持ち場へと戻りたまえ」
「分かりました」
桂木は内心ホッとしながらお辞儀をし、踵を返して部屋に戻ろうとした。当然まだ危険が完全に過ぎ去ってくれたわけでは無いが、事情聴取という大きな危機を無事に乗り切れたために、溢れ出しそうになっていた緊張感が、このとき一瞬だけ小さく萎んでいったのだった。
桂木でも乗り切れたのだから、この後木田が事情聴取でボロを出してしまうことなんて考えにくい。となると心配なのは、「犯行があった時刻には外にいた」という証言が、他の兵士の口から出てこないかどうかということだけだが、先にも考えたとおり、これはまず起こりえないと思う。
もちろん、一人でいたというのはアリバイが無いことを自白しているようなものだったが、それは他のほとんどの兵士だって同じことなので、心配する必要は無い。仮眠室で眠っていたって、その存在が起きていた者によって確認されることなんてほとんどないはずなのだ。皆眠っていたのだから。
「ところで、プログラムの書き換えに使われたというノートパソコンは、犯人に繋がる手がかりとはならないのでしょうか?」
自分達の犯行に詰めの甘かった点が無かったか心配だったので、桂木はこの機会に確かめておこうと思い、振り返って聞いた。なにやら話し合いを始めていた上官たちだったが、御堂が一度話を切ってこちらの問いかけに答えてくれた。
「残念ながら。兵士なら誰だってIDもPASSも知っていたっておかしくはないから、犯行に使われたパソコンが特定できても、そこから犯人を搾り出すことは不可能だ。指紋でも残っていれば話は別だが、そんなマヌケなヘマは誰だってしないだろう。というのが、現在の我々の見解だ」
「そうですか」
安心しながら、しかし表面上では残念そうな顔を作り、今度こそ持ち場へと戻ろうとする桂木。
「ちょっと待て」
引き戸を開こうと手を伸ばしたとき、背後から急に呼び止められた。
心拍が突然激しくなる。なにやら胸騒ぎがしたのだ。それもそのはず、桂木を呼び止めようした声が、これまで全く感じなかったようなとてつもなく重たいものだったから。
恐る恐る桂木は振り向く。大胆なアフロを頭に乗せた男の後ろ姿は、直立姿勢を保ったまま静かに微動だにしていない。
「あの……なにか……」
桂木が口を開いた直後、ぎょろりと大きく目を見開かせた醍醐一郎が、頭だけをゆっくりと回してこちらへと視線を合わせてきた。
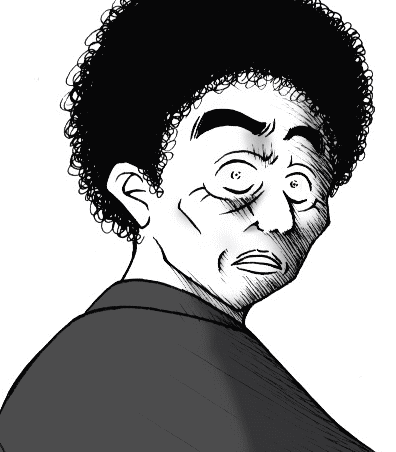
「お前、どうしてそれを知っている?」
「えっ」
それ、とはいったい何なのか。桂木は醍醐が言っていることを理解できていなかった。桂木だけではない。側に立っていた御堂一尉もまた何が起こったのか理解できていないらしく、ただ不思議そうな表情を浮かべている。
「犯行に使われたのがノートパソコンだったと、どうしてお前が知っている?」
醍醐は先ほどの質問をもっと分かりやすいように言い直す。そして初めて、桂木は自らが犯した失態に気がついた。
「プログラムの妨害に使用されたコンピューターが判明したのは、ほんのつい先ほどのこと。以降、犯行について判明したことは、一切他の者に伝えないよう技術兵には命令していたはずだ」
そう。プログラムの妨害にノートパソコンが使われていたことなんて、内部犯の可能性があるとたった今知ったばかりの一兵士が、もとより知っていたはずなどない。知っているのは、事態の究明に直接当たっていた技術兵数名と、上官である醍醐と御堂だけのはず。
他にもそれを知っている者がいるとすれば、犯行を行った張本人、すなわち犯人そのものでしかないのであった。
【残り 五人】 |
