「ただいま」
仕事から帰ってきたばかりの父が玄関扉に鍵をかける、ガチャンという音が聞こえた。キッチンで夕食の用意をしていた母は手を拭いてから、廊下を歩いて父のところへと向かい、「おかえりなさい」と言って鞄を受け取った。
「ご飯もうすぐできるけど、先にお風呂にする?」
「飯が先でいいよ」
二人の話し声がだんだんとリビングに近づいてくる。ソファーに座ってテレビを見ていた小学生の息子は頭を上げ、部屋と廊下を隔てているドアのほうを振り返った。
「おかえり」
「ただいま」
息子はリビングに入ってきた父の姿をじっと見た。グレーのスーツをばっちりと着こなした、いかにも仕事の出来そうな男。中学教師である彼は実際に真面目で、家にいてもいつも学校のことを考えているような人だった。どのようにして授業を進めていけば良いか、休みの日にはよく計画をたてている。ヘアピンを使って一糸乱れぬ七三に髪型をセットしているあたりは、まさに隙の無い性格の持ち主ということを表しているかのようだった。それでいて他人に対する思いやりもあったため、生徒達からもそれなりに慕われていたらしい。
ネクタイを外して上着を脱ごうとしていた父に向かって息子は言った。
「なんか疲れていそうだね」
すると父はグレーのスーツをハンガーにかけながら、「んっ?」と息子のほうを向いた。
「なんでそう思う?」
「顔が少しげっそりしている」
「ああ、それは気付かなかったな。ここ最近期末試験の問題作りに追われていたから、それでちょっと疲れが溜まってしまっているのかもしれないな。でもまあその作業は今日で終わったし、心配しなくても大丈夫だよ」
ははは、と父は笑った。楽しい時はもちろんのこと、疲れているときも苦しい時も、いつだって笑顔を絶やさない人だった。
笑顔は良い。見ているとこちらも自然と明るい気分になれる。だから思った。自分も父のように笑顔が素敵な人間になりたいと。
「父さんのことよりも、お前の方こそ劇団の稽古で疲れていないか?」
「そんなことないよ。役を演じることは、たとえ練習とはいっても楽しいし。そうそう、僕、次の舞台では主役をやることになったんだよ」
「本当? やったじゃないか」
二人で仲良く話していると、「ご飯用意できたわよ」という母の声がキッチンから聞えてきた。
父はそれに応えながら息子との話を中断し、テーブルへと歩いていく。息子はキッチンへと向かい、盆を持って皿を運ぶ母の手伝いをした。
このころ、山峰家は平凡ながらも幸せな日々を送っていた。
「事の発端は今から五年前だ。竹倉学園で起こった学校火災で、俺はたった一人の父親を亡くしてしまった」
多種多様の野生植物達に囲まれている中で、利久は苦虫を噛み潰したような顔をした。
「父親?」
「山峰道夫という中学教師だ。仕事一筋で家庭を顧みないところがほんの少しだけあったが、俺はそれでも父のことが好きだった。仕事から帰ってきて俺に接する彼はいつも笑顔で、面と向かって話しているとなぜか明るい気持ちになれた」
利久が自らの家族について話してくれたことなんて今まで無かった。そのため、彼の父親が竹倉学園大火災で亡くなっていたとは初耳だった。
幹久は驚いてから、すぐにおかしな点に気がついた。利久の苗字は湯川。父と子の間で何故か苗字が異なっている。
「俺は父と母と三人で、それなりに幸せな日々を送っていた。だけど、そんな生活は突然終わりを告げることとなった」
ふいに利久が悲しそうな目をした。
「俺がまだ小学校に通っていた時、ある頃を境に父の様子がおかしくなっていったんだ。目が据わって手足が小刻みに震えているのを何度も見た。初めの頃は何かの病気かと思って、母と二人で心配しながら病院に行くよう何度も促していたよ。だけど父は聞く耳も持たず、容態はさらに悪化していく一方。それどころか父は母のことを口うるさいと言い出し、しまいには夫婦喧嘩まで起こる始末さ」
周囲の湿った空気がだんだんと重くなって圧し掛かってくる。
「意思の疎通が出来なくなった夫婦の関係は、驚くほどあっさりと崩れた」
「離婚……か。ああ、だから親子なのに苗字が違うんだ」
「そう。父親一人を残して俺と母の二人が家を出たんだ。そして父が親権を失ったため、俺は母親の旧姓である湯川を名乗ることになった。その直後だったよ。父が学校の中で頭から灯油をかぶり、自らの身体に火をつけたのはね」
竹倉学園大火災は、教員の一人が校舎の中で焼身自殺したことが原因で起こったと、かなり昔にニュースやワイドショーで流されていた。しかし、その教員が利久の父親だったなんて、幹久には今日まで知る由も無かった。
「独りぼっちになってしまったお父さんは……、これからの人生を悲観して自殺してしまったわけか……」
幹久が掠れた声で言った。しかし利久は「違う」と真顔でそれを即座に否定する。
「父の死について不審に思っていた俺の耳に、ある噂話が飛び込んできた。山峰道夫はドラッグに手を出していて、精神的におかしくなって自らに火を放った、と。その可能性は十分にありえると俺は思ったね。離婚する前に父の様子がおかしくなっていたのも、薬物中毒の症状だったのだとしたら説明がつくからな。母にいくら勧められても病院に行かなかったのは、ドラッグの使用がばれるのを恐れていたから」
「それで、その噂話は真実だったの?」
「ああ。警察が父の家を捜査したところ、紙に包まれた白い粉末が少量だが見つかったそうだ。エンゼルというドラックだったと聞かされた」
それもまた初耳だ。妙なことに、竹倉学園大火災に関する報道の中でエンゼルという単語が出てきた記憶は無い。
「エンゼルとは、現在密かに出回っているホワイトデビルという薬物の前身らしいが、これがまた結構ヤバイ薬でな。精神に異常をきたして思考能力が急激に低下したり、さらには幻覚を見てしまったりもするらしい」
「お父さんはどうしてそんなものに手を出したんだ?」
「エンゼルってのは至高の快楽を得ることが出来ると言われていたからな。最初、仕事に疲れた父自身が、一時の快楽を求めて興味本位で使ったのかと、俺は勝手に思っていたよ。だけど、一冊の日記帳が見つかって、その考えは間違いだったと分かった」
「何が書かれていた?」
「薬に溺れた父の悲痛な叫びさ」
話を続けながら利久は天を仰ぎ、顔をぐしゃぐしゃに歪めた。
「日記の始まりにはこう書いてあった。『騙された。勧められるがまま私が使い続けてきた薬とは、どうやらとんでもない代物だったようだ』とね。そう、父は誰かに騙されて薬を使ってしまったんだ。日記の続きにはエンゼルの症状に苦しみながら送る日々について、長く長く綴られていたよ。竹倉学園が燃える前日に書かれた部分もあった。あれはもうほとんど悲鳴に近かったね。最後の一行が『誰か助けてくれ』だもんな。分かるか? あの時俺がどれだけ大きな衝撃を受けて、父の苦しみに気付いてやれなかったことを悔やんだか!」
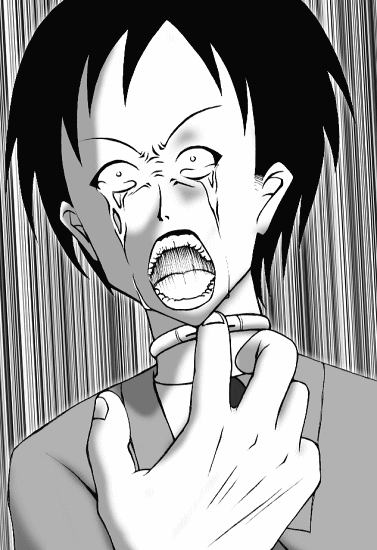
感情的になった彼の言葉の最後のほうは、ほとんど怒鳴り声に近かった。そして意外なことに、冷酷な面を散々見せ付けてきた利久の目から、大量の涙が溢れ出してきている。当時を振り返るというのは、彼にとって相当辛いことなのだろう。
辺り一帯を雷光が照らし、幹久の目に映る景色の全てが一瞬だけハイライトとシャドウの二つにくっきりと分割された。数秒後、ごろごろと空が唸りを上げた。
「俺は父のことが好きだった。だから両親が離婚してからも、父の様子が変わってしまったのは、仕事による疲れのせいか何かだったのだと信じていた。それだけに、誰かに騙されて薬物なんかに手を出していたなんて知ってしまった時のショックは大きく、それから長い間心の傷に苦しむこととなったよ」
利久は一呼吸入れるために、話の中に数秒の間を挟んだ。ここから少し場面が変わるらしい。
「時間を少し進めよう。今から二年半ほど前、松乃中等学校に入学した俺は、後の運命を左右する非常に重大な出会いを果たした。北見泰昭教諭とのね」
北見先生といえば科学の授業を担当すると同時に、親身になって生徒の相談を聞いてくれるとのことで人気の高かった人物だ。そして東大卒という高学歴の持ち主でもある。松乃中等学校大火災が起こる二週間ほど前に交通事故で亡くなったと聞き、クラス中が騒然となったのを、今も鮮明に覚えている。
「中学に入ってからも心の傷が癒えていなかった俺は、表面的には平静を取り繕っていたが、内面ではもう限界を迎えようとしていた。長きに渡って一人で悩み苦しんできたために、精神がボロボロになってしまっていたんだ。すると北見先生は目敏く俺のそんな状態に気がついた。無理矢理に俺の苦しみの元を聞きだして、望んでもいなかったのに勝手にカウンセリングを始めたのにはさすがに驚いたよ。気がつくとほぼ毎日のように理科準備室へと呼ばれ、彼と面と向かって話すようになっていた」
理科準備室の中には科学を担当していた北見先生専用の机と椅子が置かれていた。北見先生自身は職員室よりもそこにいる時間のほうが長かったため、彼に相談事をしに行く生徒達は皆、いつも理科準備室を訪れていた。利久もその一人だったということだ。なんか意外。
「はじめは警戒していた俺も、対面して話しているうちに次第に心を開いていって、最終的には悩み事の全てを彼に打ち明けるようになっていた。両親が離婚した直後に竹倉学園の火災で父が死んだこと、その一件にエンゼルというドラッグが関わっていたらしいということなど、何から何まで話してしまったよ。それだけ北見先生のことを信用してしまっていたというわけだ」
幹久はあまり世話になったことが無いので詳しくは知らないが、北見先生は的確なアドバイスと意見を述べて相談者の心を上手く和らげてくれると誰かが言っていた。そのため彼が相手だと安心して話をしてしまうというのも、なんとなく納得できる。
「ところがだ。毎日のように俺の話を聞いてくれていた北見先生は、ある日突然、交通事故で亡くなってしまった」
車での通勤途中に起こった衝突事故で、ハンドルに強く頭を叩きつけて即死したのだ。
「その一件でまた大きなショックを受けたね。大切な父親に死なれた次に、親身になって話を聞いてくれた先生まで亡くなってしまうなんて、と。でもな、北見先生が事故死してからおよそ二週間後、俺は彼のとんでもない秘密を知り、そして自らの過ちに気付いたよ」
「どういうことだ」
幹久は眉をひそめた。
「ある日、無気力となった俺はフラフラと学校の中を徘徊し、気がつくと理科準備室へと訪れていた。まだ北見先生に未練が残っていたんだろうな。部屋の中は先生が死ぬ前と全く変わっていなかった。しかし、いつも二人で話をしていたそこにはもう誰の姿も当然無かった。一人で部屋の真ん中に立っていると、なんだか目の奥から熱いものがこみ上げてきたよ。俺はたまらず踵を返して理科準備室から出て行こうとした。そのとき、妙な光景が視界の中に飛び込んできた。北見先生の机のちょうど真上で、天井の板が一枚、僅かにだがずれていたんだ。俺は気になって、机を踏み台にして天井板を外してみた。そしたら、驚いたよ」
爪の先から血が滲み出てきそうになるほど、利久が強く拳を握り締める。ついに話の核心部に触れるのだと、幹久はなんとなく感じ取った。
「天井裏へと顔を覗かせた俺の目の前に、白い粉末の詰まった袋が大量に姿を現したんだ。全て父を破滅に追い込んだ薬物と同じ、エンゼルだったよ」
「まさか」
「人柄にまんまと騙されてしまっていた自分のことを、あのときほど情け無いと思ったことは無かったね。北見先生は教員生活を送りながら、裏では薬物の売買をしていた。そして彼にとって松乃中は職場であると同時に、エンゼルを大量に保存するための薬物貯蔵庫でもあったわけさ」
信じられない。かつて普通に通っていた学校の中に、そんなとんでもない秘密が隠されていたなんて。
あまりに衝撃的な話を聞き、幹久の頭の中はもう混乱してしまいそうだった。
「俺は思ったよ。父がエンゼルに手を出した根源には、北見先生の存在があったのではないか、とね。父に直接エンゼルを渡していたのは、もっと下っ端の売人だったのかもしれないけど」
「でも、北見先生は自ら薬物をばら撒いておきながら、どうして湯川くんの相談なんかに乗ったのだろうか」
「さあな。自分が撒いた薬が原因で苦しんでいる俺を間近で見ているのが楽しかったか。僅かにでも罪悪感を覚え、せめてもの償いとして俺の相談に乗ったか。いずれにしろ、俺を裏切った彼を許すつもりなんて毛頭無いがね」
何も知らないような顔をして相談に乗ってくれていた教師が、実は苦しみの原因を作っている人物だった。利久が北見先生のことを裏切り者呼ばわりするのも無理は無い。口調から、彼の怒りがどれほど大きいものなのか感じ取れる。
「そこからはもう無意識のうちに身体が動いていた。平穏な日々を奪った悪魔の薬を全て消し去ろうと、俺はライターに火を灯した。炎は一気に広がったよ。天井裏が崩れて大量のエンゼルのちょうど真下にあった理科実験室が、瞬く間に灼熱地獄と化した」
「そのとき、湯川くんはどうしていたの?」
「天井裏から理科準備室へと下りていたさ。が、もうどうなっても良いと思えてきて、気力を失った俺は外に逃げようとはしなかった。たちまち煙が部屋に立ち込めてきて、そのまま意識を失ったね」
なるほど。そしてその直後に理科準備室の中で倒れていた利久は、先生か誰かに外へと運ばれ、そのまま病院に搬送されたというわけか。
「幸か不幸か、あれだけの惨事の中にいながらも、俺は一命を取りた。昔から悪運は強かったからな。大した負傷も無かったため、すぐに退院することができたよ。数週間後には皆と一緒に、普通に梅林中へと通うようにもなっていた」
ほんの一瞬だけ穏やかな表情を見せた利久。しかしすぐに、「だけど」と氷のように冷たい目をした。
「憎しみに満ちた俺の心は、いつまで経っても晴れはしなかった。かつて松乃中学校に通っていた生徒達――お前を含めた被災者特別クラスの人間たちがまだ生きていたから。俺は、お前ら全員を殺してやりたいとずっと思い続けていた」
「なんだって」
幹久は驚いた。松乃中の生徒達は、薬物の件や利久の父の死に関係してはいないはず。どうして殺意を向けられなければならないのだろうか。
「俺がお前達を憎んでいた理由なんて、そりゃあ分からないだろうな。実はさ、エンゼルを使っている人間の中には中学生って結構いたんだよね。塾通いとか受験勉強なんかを長期間続けて疲れた学生なんかが、それこそ一時の快楽欲しさに薬を求めてしまうケースは多いらしいんだ。ある時に俺は思ったよ。そんな奴らがごまんといるから売人達が調子に乗って、この世界にエンゼルという悪魔の薬を大量に持ち込んでくるんだとね」
「薬物が流通する土台を作り上げた学生達を、皆殺しにしてやりたいと思ったわけか」
「そういうこと」
「でも、薬を使っていた者が松乃中にいたとしても、そんなのはごく一部の人間だけだろう。関係の無い子たちをも巻き込む必要は無いはずだ」
反抗的な態度をとる幹久に、利久は再びマシンガンを向けた。
「確かに大半の生徒はエンゼルとは関係なかったかもしれない。だけど誰だって何がきっかけでいつ薬に手を出すか分からない。売り手側の人間達にとって、お前らは釣り針のすぐ側で泳ぎ回る魚と大して変わらなかっただろう。逆に言えば、お前らが存在していなければ、エンゼルなんて薬物をわざわざこの地に持ち込んでくる人間なんていなかったかもしれない」
撒き餌に群がる魚達がいなければ釣り人はやってこない。それと同じように、薬の買い手がいなければ売り手はやって来ないはず。そういうことか。
「だから俺はこの際、エンゼル――今はホワイトデビルだったか、とにかく忌まわしい薬物をこの地から消し去る為にも、薬物の売人達を引き寄せた者達全員を殺してしまえばいいと思ったんだ。それからはもう、憎きクラスメート達が苦しんで死んでいくのを見ているのが、楽しくて仕方なかったね」
「馬鹿げている……」
幹久が押し殺したような声をだした。利久はピクンと眉を動かしてして、「なに」と不快感のこもった声を返す。
「いったい何が馬鹿げていると言うんだ」
「考え方全てだ。たしかに僕らという存在が、結果的にはエンゼルを引き寄せることになったのかもしれない。でも、だからと言って殺してしまいたいと思うなんて、やっぱりおかし過ぎる。そんなのはただの八つ当りか逆恨みだ!」
「貴様っ!」
幹久の言葉に激昂した利久が、すかさずスコービオンの引き金を引いた。無数の銃弾が幹久の身体を次々と貫いていく。腹部の付近にある臓器という臓器が破壊されて、ピンク色の身が傷口から飛び出していた。もはや肉体の修繕は不可能な状態だと、一見して分かる。
「俺の気も知らないで勝手な事を言いやがって。やっぱりお前はムカツク野郎だ。てめぇだって妹を助けるために、何の関係も無い叶と安藤を殺しただろうが。お前も俺も、もはや同じ穴のムジナなんだよ」
そう言われてしまうと何も言い返せない。たしかに幹久がやってきた殺人も自己中心的なことで、決して許されることではなかった。
いくら他に妹を助ける方法が無かったとはいえ、一時の感情にまかせてよく考えずに行動してしまった自分が、今更ながら情け無く思えた。
「もういい。お前の顔を見ていたらイライラしてくる。とっとと死んでもらう」
と言うと利久はスコーピオンサブマシンガンを桜の手に握らせた。殺意のこもった目つきから推察するに、今度こそ余計な遊びを挟まずに終わらせるつもりだ。
幹久は思った。ああ、これはクラスメートの血で手を汚してしまったことへの報いなのだろう、と。自分はここで殺されてしまっても文句なんて言えない立場なのだと実感すると、何故だか死ぬのも恐くは感じなかった。
しかし、心残りは一つだけあった。それは妹の笑顔を再び見ることができなかったということ。自分は死んでも構わないけど、最後にもう一度だけ、あの輝かしい表情を自らの目に焼きつけたかった。でも、それももう叶わぬ夢。
桜……。
幹久の霞んだ視界の中で、桜はマシンガンを握った手をゆっくり前へと突き出す。ほとんど間を置くこと無く、利久は腕組みしながらついに命令した。
「殺せ」
一瞬時が止まったように感じた。ニ年前の松乃中等学校大火災以来、感情を失ってしまった桜はもちろん、冷ややかな目をしている利久も一切表情を動かさなかったから。そしてそれ以降、利久の表情が変わることは二度と無かった。
ドンッと大きな爆音が轟いて、利久の首から上が突然消失してしまったのだ。そのすぐ横で爆風を受けた桜が吹っ飛ぶ。
「えっ」
ぼんやりと見ていた幹久は目の前の状況を一瞬掴むことができなかったが、何が起こったかすぐに理解した。どういうわけか利久の首輪が爆発したのだ。誤作動なのか、政府の人間たちが意図的に操作したのかは分からない。ただ利久が即死してしまったことだけは確かだった。
本当に一瞬の出来事だったので、本人は苦しむ暇もなかったに違いない。
胸の高さに組んでいた腕を解きながら、利久はゆっくりと倒れた。
 湯川利久(男子二十番)――『死亡』 湯川利久(男子二十番)――『死亡』
【残り 八人】 |
