利久が吐き出した言葉を耳にして、幹久は鎖でがんじがらめにされてしまったかのように身体を固めてしまう。一瞬、相手が何を言っているのか理解することも出来なかった。
ほんの数メートル向こうでは、マシンガンを手にする利久が、にやつきながら「さあお前の番だ、行ってこい」などと言って桜の身体を前に押し出そうとしている。
桜は全く抵抗することなく、それどころか小さく頷いて自ら前へと歩み出てきた。
「よーしよし、いい子だ」
利久は真っ白い頭をレインコート越しにやさしく撫で、持っていたマシンガンを後ろから差し出す。
桜はそれを受け取るや否や、ガチャンと音をたてながら前で構え、迷うことなく発射口の向きを実の兄の胸元へと合わせた。
「おっと、まだ撃つなよ。試合開始は俺が合図してからだ」
桜が誤って早くも引き金を絞ってしまわぬように、間に入って制する利久。
今、目の前で起こっていることが、幹久には現実なのかどうか分からなかった。というより、嘘か、あるいは幻だと信じたかった。いくら桜が自我を失ってしまっているとはいえ、実の妹である彼女がこちらに銃を向けるなんて、全く考えられないことだった。
幹久が茫然と立ち尽くしていると、またあの意地の悪そうな笑い声が聞こえた。
「さあお兄さんや、そっちもさっさと武器を構えなよ。妹を殺すことができれば、お前は助けてやると言っているんだ」
彼はギラギラと光る目をこちらの手もとへと向けている。幹久が持つ唯一の武器、ツルハシを見ているのだ。
「ツルハシ。少々頼りないが、殺傷能力に関しては問題ないだろう。まあそれはもうお前自身で実証済みか」
そいつで安藤を殺したんだもんな、と彼は言いたげ。幹久は何も言い返せない。
「なにをしている。お前はもうクラスメートを二人も殺しているんだ。今更妹一人手にかけるのに躊躇することなんてないだろう」
しかし幹久は武器を構えることなんてできなかった。たった一人の大切な妹に凶器を向けるという場面を想像することすら、頭は拒絶してしまうのだ。
「……できない」
幹久がぽつりと言うと、利久は両手を腰に当てたまま、急に「ああっ?」と不機嫌そうに声をあげる。
「できないって、何がだよ」
「桜と殺し合うなんてとてもできない。僕は自分の命を失ってでも桜を救いたいと思っているんだ」
幹久は身体から力を抜いた。すると握っていたツルハシが手から落ち、半分泥沼と化していた地面に深く突き刺さる。利久はそれを見て、ふぅと溜め息をつき、あきれた顔をした。
「お前は本当に駄目な奴だな……。もういい」
利久は両方の目をグルリと動かしてそのまま桜の顔へと向ける。幹久は全身に何か冷たいものが走るのを感じた。
「やめろ! 撃つな、桜!」
嫌な予感がした刹那、幹久は必死に叫んでいた。しかし横からの「撃て、桜」という言葉にかき消されて、桜の耳に兄の悲痛な声は届かない。
桜の身体を制していた利久の腕が遮断機のように上げられた途端、小さな手が握る銃器からフラッシュライトのような眩い光が連続して放たれた。続いて、タタタタタンッ、と火薬の破裂する音が森林中に響く。
幹久は身体中を焼かれたような感覚を覚え、そして後方へと飛んで倒れた。
一瞬頭の中が真っ白になってしまったが、何が起こったのかすぐに理解できた。撃たれたのだ。実の妹に。
身体中のあらゆる部位から血が滲み出し、泥だらけだった制服が今度は赤く染っていく。
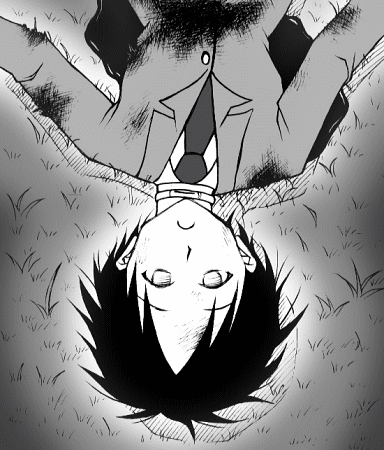
「妹とは戦いたくないって? へっ、お前がそう言いだすことくらい最初から分かっていたさ」
銃弾に手足の一部分を抉られて、幹久はもう立ち上がることすらままならない。そんな彼の側に利久が悠々と歩み寄ってくる。
「たださ、なんとなく最後にもう一度、お前で遊んでみたくなったんだよな。実の妹に銃を向けられたお前が、驚愕の表情を浮かべながらどんなリアクションをとるのか、是非見てみたくなったのさ」
ぼんやりと真上を向く幹久の目に、男の笑顔が写り込む。しかし幹久はそれが誰のものなのかほとんど認識できていなかった。妹に撃たれたというショックの大きさのあまり、一時的に思考力が著しく低下してしまっていたのだ。
「つまりだ。俺は戦意を喪失したお前に桜が負けることは無いと初めから見越したうえで、二人で殺し合え、なんて無理難題を押し付けたわけだ。彼女はなかなかに優れた駒だから、まだ手放す気は無いんだよな」
その時、遅れて近づいてきた桜が利久の後ろからゆっくりと顔を覗かせた。すぐ前に立つ利久の姿なんて全く視界に入らなかったというのに、なぜか桜の方には自然と目が向いた。
「さ……くら……」
幹久は倒れたまま必死に手を伸ばすが、桜には全く届かない。
まだ自我を失っていなかった頃のかつての妹なら、そんな哀れな兄の姿を見たら、心を通じ合わすべく自分からも手を伸ばしてくれたであろう。しかし今、彼女は感情の篭っていない冷たい目でこちらを見下ろすばかりで、兄のことを想う気持ちなんて塵ほどにも見せてはくれなかった。
髪の毛全てが真っ白に染まった妹の姿を見て、幹久は思った。ああそうか、桜は本当に僕のことなんて忘れてしまっていたんだ、と。すると突如、堪えようとしていた涙がまた勝手に溢れ出して止まらなくなってしまった。
松乃中等学校大火災に巻き込まれて桜の様子が以前と変わってしまってからも、彼女はまだ微かには自分のことを覚えてくれているに違いないと、幹久は今日まで信じてきた。それがたった今、違うと分かってしまったのだ。
「そうそう、その顔いいね。妹に銃で撃たれたというのがよっぽどショックだったと見える」
幹久の気持ちも知らず――いや、知ったうえでなのか、利久は心底楽しそうな顔をした。周囲の木々が枝先に群がる葉を一斉にざわつかせる。
「ところで、君の妹はもう少しの間有効活用させてもらうよ。兄を殺し、それから残るクラスメートを全員殺害しろ、と桜には既に命じてある」
幹久は、ぼんやりと上へと向けたままだった目の前に、何かが急激に迫っているのを感じた。側に立っていた利久が低く屈んで、幹久の顔をごく近い距離から覗き込んでいたのだ。それでようやく、幹久の視界に写る相手の姿が鮮明になった。
「どうして……、どうしてそんな酷いことをするのさ……」
涙ながらに問う幹久。何故、何の罪も無い桜が殺人者なんかに仕立て上げられ、実の兄を殺すよう命じられなければならないのか。いくらプログラムの最中だとはいっても、この仕打ちはあまりに酷すぎる。
マシンガンの弾に貫かれた全身の痛みと、妹に銃を向けられたという事実に苦しんでいる幹久とは対照的に、利久は非常に生き生きとした顔つきをしていた。そして「前にも言ったことがあるだろう。楽しいからさ」とあっさり答える。
「そ……それだけの理由で?」
「……ああ、それだけさ」
すると利久は突然、「なあ、いいもの見せてやろうか」と言って、桜の身体を自分のほうへと引き寄せた。
「さ、桜に何をする気だ」
「まあまあ、それはこれからのお楽しみだ。よーく見とけよ、お兄さん」
利久は裂けそうになるくらいに口の端をつり上げ、そして驚くべき行動をとった。レインコートの隙間から衣服の内側へと手を滑り込ませ、そして汚れを知らない桜の清い身体を触り始めたのだ。
「へぇ。幼児体型には興味が無かったんだが、肌の手触りはなかなかのもんだな。あー、でも胸はもっとなんとかしたいところかな」
「やめろ! いったい何のつもりでそんなことを……」
「いいから、お前は黙って見ておけよ」
利久の手はワイシャツの下で這うように、桜の全身をまさぐっていく。浮かび上がるレインコートのしわが、利久の手の動きに合わせて変形し、とてつもなくいやらしい。
エスカレートしていく行為を、幹久はもう黙って見ていることは出来なかった。悔しさのあまり眉間に深くしわを寄せて、噛み締めた歯からギリギリと音を立て始める。
「いいねその表情。この娘をさらに汚していけば、もっと良い表情が見られるのかな」
幹久はもう沸きあがる怒りを抑えることはできなかった。プログラムに巻き込まれてしまった為に仕方無く人の道から外れた行動をとってしまったのではなくて、利久はただ自らの欲を満たすためだけに、数々の手段を用いて幹久たち兄妹を弄び、苦しめてきたのだ。
ばらばらに散ってしまっていた幹久の思考が、まるで怒りという感情に吸いつけられたかのよう集まり、そして一つの考えを形成した。
このまま利久の思い通りにさせてはならない。自分は死んでしまうとしても、桜を利久の欲を満たすための道具にさせたままにしてはいけない。
「へぇ。驚いたな」
利久は細い目を少しだけ見開いて顎をしゃくった。手足に深手を負ってしまっている幹久が、ゆっくりではあるが痛みを堪えながら立ち上がろうとしていたのだ。
「それだけボロボロになっていながら、まだ動くことが出来るんだ」
マシンガンを持つ手を下ろしたまま、生まれたばかりの小鹿のごとく手足を震わせながら立ち上がろうとする幹久の姿を、利久はじっと見つめている。
柔らかな土の上に手をつき、膝を立てて、と、幹久は徐々に自らの身体を地面と垂直に立てていく。目線の高さが利久と同じくらいになるまで、時間は一分もかからなかった。
幹久は強い口調で言った。
「桜を取り返し、そしてお前の下らない欲望から成る支配を、今ここで終わらせるんだ!」
【残り 九人】 |
