コンテナ置場じゅうに鳴り響くサブマシンガンの銃撃音。親友の一人である熊代フミを探し回っていた最中、福原千代は目を見開いて、そのまま表情を固めてしまった。
「銃声……?」
当然、千代と行動を共にしていた松原雛乃の耳にも、その音は届いていた。そして、絶望感を味わうこととなった。
サブマシンガン……そんな強力な武器、持っている人物なんてそうそういるはずが無い。確認するまでもなく、撃ったのは湯川利久に操られている白石桜であろうと容易に想像することが出来た。そして彼女の標的となったのは――。
「フミ……」
千代が友人の名を小さく口にした。
そう。このコンテナ置場という限られた区域の中、自分達以外にも誰かが隠れていた可能性はあるが、それよりも、雛乃達とはぐれてしまっていたフミが敵に見つかり、そして彩音と同じようにマシンガンから発射された鉛雨の餌食になってしまった、と考える方が自然に思えた。いや、それ以前に、銃声とほぼ同時に聞こえた女の悲鳴はおそらくフミのものであったし、襲われたのが彼女だというのは間違いないはずだ。
間に合わなかった。自分達がもっと早くフミを見つけ出せていたなら、彼女の命を助けることが出来たかもしれないのに……。
友の死を感じ取り、雛乃は足を止めてうなだれる。すると、こちらの内心を察したのか、続いて千代もその場に立ち止まった。
「だ、大丈夫だよ。襲われたのは確かにフミなのかもしれないけど、そこから上手く逃げ出せたかもしれないし」
落胆している友人をなだめようと千代が顔を覗き込んでくる。しかし雛乃は、千代には他人のことなんかに構っている余裕など無く、自分自身を落ち着かせることだけで精一杯であるように思えた。彼女の声が震えていたから。
フミは上手く逃げ出せたかもしれない、という彼女の言葉も、雛乃の心配をほぐすためではなく、自らに言い聞かせるためのものだったのではないだろうか。
だが千代が何と言おうと、フミの生存は絶望的という考えは変わらなかった。フミの武器である脇差はマシンガンに対抗するにはあまりに頼りなさ過ぎる。それに、四人で固まっていた先ほどはマシンガンの狙いが分散した為に、彩音以外は運良く難を逃れたが、今フミは一人ぼっちだ。しっかりと狙いの定まった銃口から吐き出される何発もの弾丸から、特別足が速いわけでもない人間がそう都合よく逃れられるはずなど無い。
雛乃はもはや確信していた。フミはもう殺されている、と。おそらく千代も言葉とは裏腹に、頭の中ではそのような考えを浮かばせているはずだ。
「千代……もう行こう」
千代がこちらに顔を向けて、至極小さく頷いた。「行くあては無いけど、とにかくここから離れたい」という雛乃の思いを感じ取ったのか、「何処へ?」などと聞いてきたりはしなかった。
フミが殺されてしまった以上、雛乃たちにはもうこの場に留まり続けなければならない理由など無い。さっさと安全なところにまで逃げるべきだった。千代が言っていた「湯川を殺して桜を開放してあげる」なんていう目的も残されてはいるが、それを行動に移すにはあまりにリスクが大きすぎる。グレネードランチャーという強力な武器をもってしても、マシンガンが相手では勝利は確実なものではない。
そんな勝てるのかどうかも分からない勝負、無理に挑むべきではない。利久を倒す、なんて話はあくまでも「フミを探すついで」にすぎなかったし、殺された友人の敵討ちというのも、実は全く意味の無いこと。死んだ人間は何をしたって生き返りはしないのだから。
一時の怒りに任せて無駄死にするのは避けるべき。触らぬ神にたたりなし、だ。
少し前は怒りの炎を燃え上がらせて、利久を倒すと誓っていた千代も、フミまでもが殺されて憔悴しきってしまったのか、もうその考えを主張したりはしなかった。自分から利久たちに挑むということは、さらに雛乃をも危険に巻き込んでしまうことになる。その辺りも彼女を躊躇させる要因であったに違いない。
雛乃は千代の手を引いて歩き出そうとした。
「大丈夫。一人で歩けるから」
しっかりと繋いでいた友の手を優しく解いて千代は顔を上げる。落胆しているのは一目瞭然だったが、自分はまだ元気だと頑張ってアピールしようとしているのが見て取れた。だから雛乃は何も言わず彼女に従い、手を引くのはやめることにした。
「とりあえず山の方へと逃げることにしよう」
まっすぐ西へと移動すれば、コンテナ置場を抜けてすぐに山の中へと逃げ込むことが出来る。隠れる場所の多い山中は、いつ敵に襲われるか分からないという危険が常に付きまとうが、逆にこちらが茂みの中にでも身を潜めてさえいれば、簡単に利久たちに見つかってしまうことも無いはず。雛乃はそう考えたのだった。
「問題は、無事にコンテナ置場から出られるかどうか、か」
千代の言うとおり、それは大きな不安要素であった。桜に襲撃された際に、雛乃と千代は港に近い東側へと逃げ込んでしまった。だから西へと抜けようとするには、見通しの良い中央通りを横切らなくてはならない。
「見つからないためには、中央通りを素早く渡る必要がある」
「うん。一瞬で駆け抜ける」
意見一致。二人は顔を見合わせて頷き合った。
「でも雛乃。手にそんな酷い怪我を負っていて大丈夫? ちゃんと走れる?」
銃弾に貫かれた右腕の傷の付近は、大量の血で真っ赤に染まっていて痛々しい。千代が心配するのも無理はない。
「大丈夫。怪我しているのは足じゃないんだから。ほんのちょっと走るくらい、全く問題なんて無いよ」
その返答には少しばかり嘘が入り混じっていた。腕の傷は相当深く、身体が僅かに振動するだけでも、とてつもない痛みを発する。はたしてそんな状態で、身体を大きく揺れ動かしながら「走る」なんて動作を問題なく行えるのかどうか、自分でも分からなかった。しかし、今は「NO」なんて言える状況ではない。雛乃にはこう返答する他無かったのだった。
「それじゃあ早く動き出すとしよう」
「うん。湯川たちに見つからないよう願いつつ」
「もし見つかっちゃったら、こちらも応戦するしかないわね」
千代の手の中でグレネードランチャーの重量感ある黒いボディが、一瞬怪しく光ったような気がした。これから訪れるかもしれない戦いに、まるで喜悦しているかのように。
「ところで千代、今さらだけど、彩音が殺された時にデイパック置いてきちゃったよね」
「うん。それがどうかした?」
「グレネードランチャーを持ってきたのは良いけど、弾はちゃんとあるの? デイパックの中に入っていたはずなんじゃ……」
「ああ。一応制服のポケットの中に何個か入れておいたから、一度の戦闘くらいなら何とかなるわ。でも気は抜けない。本当に彩音に続いてフミも殺されたのだとしたら、次は間違いなく私たちが狙われる」
言われなくても分かっている。辺りに張り詰める緊迫した空気に、ずっと押し潰されてしまいそうだった。
グレネードランチャーを持つ千代が前、雛乃が後ろという形で、二人は西を目指してコンテナの合間を進む。道はかなり入り組んでいるので真っ直ぐには歩けないけど、迷ってしまうようなことは無かった。誤って袋小路に入ってしまったことは何度かあったが。
一切緊張が途切れることは無かった。どの方向から、いつどんなタイミングで敵に襲撃されるか分からないから。雛乃は挙動不審に視線を様々な方角へと動かし続ける。
「ここまでは何とか順調に来れたね」
コンテナの角から頭を覗かせ、先の道に誰もいないことを確認する千代。幸いにも二人の身に災いが降りかかることもなく、問題の中央通りの手前にまで着くことができた。
「ここが一番の難所か」
「うん。見通しが良いから、素早く抜けないと何処かから見られちゃう可能性が高い」
通りの幅はおよそ十メートル。車三台が横並びで走れるくらいだ。それだけでもう分かると思うが、道の向こう側まではそれなりに距離がある。
本当に、こんなところを通って、見つからずに済むだろうか。
これだけの幅がある道の真ん中を人が横切るなんて、どう考えても目立ちすぎる。実際に難所を目の前にした途端、不安が大きく広がって、腕の痛みはさらに激しさを増したような気がした。
「傷、大丈夫?」
被弾した箇所を手で押さえている雛乃に気付いて、千代は心配そうに声をかけてくる。だが雛乃はここでも「大丈夫」と押し通すしかなかった。
「そう……。とりあえず通りを覗き込んで見たところ、湯川と桜の姿は無かった。だから今のうちに一気に駆け抜けたいと思う。いい?」
「うん」
「それじゃあ、一斉に行くよ」
千代は「いっせーのー」と小さく掛け声を出す。雛乃は腕を押さえたまま、「で」が聞こえた瞬間に走り出した。車三台分の幅なんて、普段なら大したことは無いと思うだろう。だけどこのときばかりは、たった数歩の距離でさえも、とてつもなく長く感じた。
雛乃と千代は通りを渡るとすぐに、錆の浮かぶ古いコンテナの陰へと飛び込んだ。
「緊張した」
「うん。見つかってなければ良いけど……」
少しの間息を潜めつつ、じっと身構えていた。もしも中央通りを横断するところを見られていたとしたら、敵は絶対にこちらへと向かってくる。しかしどれだけ待っても、利久も桜も姿を現しはしなかった。
「見られなかったみたいね」
ほっと一息ついた瞬間、すぐ近くから何やら大きな音が鳴り響いた。
グァァァァン。
それはまるで猛獣の鳴き声のよう。雛乃は突然のことに驚いて飛び上がりそうになった。
「いったい何?」
状況を把握しようと周囲を見回す。しかしその音の発信源となった物が何なのかは分からなかった。
「あれっ」
千代が何かに気付いたらしく、真っ直ぐ手を伸ばして頭上を指差している。その先にあったのは大型クレーンに吊るされたままのコンテナだった。
「風で揺れる空中のコンテナと、それを吊るしていたワイヤーが擦れ合った音だったみたいね」
「なるほど。それにしても凄い光景」
自分達の頭の上で揺れている塗装の剥がれかけたコンテナは、大きくてとても威圧的だった。
「って、こんなのに気を取られている場合じゃない。せっかくここまで無事に来られたんだ。早く山の中に逃げ込んでしまおう」
手招きしながら先に千代が走り出した。両脇をコンテナに挟まれた道は、もうそれほど長くは残されていないはず。あと少し前に進めば、殺意を抱く敵たちが潜んでいるこの区域から抜け出すことが出来る。
腕の痛みに耐えながら、気力を振り絞りつつ千代の後に続こうとしたとき、前方にある丁字路から黒っぽい物体が飛び出してきたのを、雛乃の視覚はしっかりと捉えた。
「千代! 止まって!」
雛乃は千代に向かって、すぐに退却するよう叫んだ。視界に入ってきた物体とは、黒いレインコートを羽織った白石桜だったからだ。てっきり後を追ってくるものかと思っていたが、こちらが山側へと逃げ出すだろうと先を読み、他の道を通って回り込んでいたようだ。向こうの方が一枚上手だったというわけだ。
しっかりとサブマシンガンを構えている桜に対して、千代はまだグレネードランチャーを発砲する形を取れていない。ちゃんと周囲に注意を払っていただろうけど、まさか前方からこうも勢いよく飛び出してくるとは思っておらず、結局不意を打たれるという形になってしまったのだろう。そうなってしまっては、一瞬で対応などできるはずがなかった。
桜の手元でマシンガンの銃口が高速で白く点滅したかと思うと、同時に千代の背中、手、足、頭、と身体中のあらゆる部位で赤い花が咲き乱れた。千代の身体はそのまま後方へと飛び、雛乃の足元に崩れ落ちる。
「千代!」
雛乃はすぐに屈んで友の顔を覗き込む。しかしすぐに吐き気を覚えて目を逸らした。ど真ん中に一発の銃弾を受けた頭蓋骨はひび割れて大きく歪み、生きていた頃の千代の面影を完全に失わせていたのだった。
「い、嫌ぁぁぁぁぁぁっ! 千代! 千代っ!」
もう一度友の名を呼んだ。だが、それに対して千代が反応することはなかった。
千代までもが……死んだ……?
丁字路の方から、カシャン、と金属の鳴る音がした。桜がマシンガンのマガジンを新たに入れ替えているのだ。だが雛乃の耳にその音は届いていなかった。
忘れようとしていた過去の事件に関わっていた者たちが皆死んだことによって、硬く閉ざされていた引き出しが勢いよく開き、蘇った記憶が彼女の頭の中を一瞬にして支配してしまったのだった。
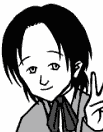 福原千代(女子十七番)――『死亡』 福原千代(女子十七番)――『死亡』
【残り 十三人】 |
