「ゆうに百キロはあるな」
積み上げられている硝酸アンモニウムの山へとゆっくり歩み寄りながら圭吾は言った。五キログラムと書かれている袋は、数えるまでもなく二十以上はあると一目瞭然。さすがに農家だけあって蓄えている肥料の量が桁違いだな、と千秋は思った。
「まあ、探していた物が見つかったっていうのはよかったけれど、それで、ここからどれだけの量を持ち帰れば良いんだっけ?」
「できるだけ多く、持ち運べるだけ持ち帰ろう。ダムの水門の強度が未知数である以上、どれだけの爆薬を製造すれば事足りるのかも分からないからな。蓮木からは出来るだけたくさん確保するよう頼まれている」
もしも材料が足りなくて、水門を破壊できるだけの爆弾を用意できなければ、とても笑い事なんかでは済まされない。同じ道をもう一往復するだけの体力も残されていないので、今回だけで十分な量の硝酸アンモニウムを確保する必要があった。幸いにも他の爆弾の材料はどれも、千秋たちが拠点としている病院で有り余るほど見つけていたので、持ち帰った硝酸アンモニウムの量がどれだけ多くとも、全て爆弾の製造にまわしてしまうことも可能なはずだ。要するに、少なくて困ることはあっても、多すぎて邪魔になることなんて無いということ。大は小を兼ねる、だ。
しかし――。
千秋には一つ気がかりなことがあった。一つにつき五キログラムもあるという硝酸アンモニウムの袋は、ほとんど米袋の大きさと変わりない。飲食店松乃屋の看板娘である彼女は米の袋の重さというものを身体でだいたい覚えていたため、それを担ぎながら長い山道を歩くということがどれほど大変なのかも、なんとなく予想できた。それだけに、これから起こる苦労のことを思うと気が遠くなるのだった。
「まあ一袋の大きさがかなりのものだし、お前は一つ運べば十分だろう」
と言いつつ、圭吾は肥料の山から袋を二つも下ろして抱え上げようとしている。袋一つを持つだけでも十分辛いというのに、さらにその倍もの重量をたった一人で運ぼうなんて、彼の体力に底は無いのだろうか。
「これを使え」
「えっ」
自分が運ぶ分の袋を一つ下ろしたところで、千秋は急に何かを差し出された。出発前に病院内で調達したという、大きく透明なビニール袋だった。
「外に出ると、またあの強い雨にうたれてしまう。中身を濡らさないよう念のため、さらに別の袋の中にも入れて二重にしておいたほうが安全だろう」
見ると、圭吾は既に硝酸アンモニウムの袋二つをビニールの中に入れていた。何かにつけて仕事が早い。
圭吾の言葉に納得した千秋もすぐに倣って、雨に備えることにする。大切な爆弾の材料をビニールで包み、最後に口を強く縛ると、荷物の重さを前に弱気になってしまっていた心も少だけ引き締まったように感じた。といってもそれはほんの一時的なことで、肥料の袋を抱えてその重さを直に体感した途端、再び大きな不安を覚えて気後れすることになってしまったが。
「用意は済んだな。それじゃあ早速戻り始めるとするぞ。こんな所に長々と止まりつづけている理由なんて無いからな」
大きな袋二つをまとめて右の脇に抱えた圭吾と共に、千秋は出入り口のほうへと向かう。家の中はほとんど真っ暗で何も見えないに等しかったが、先の探索で家具などの配置はある程度理解できていたため、物に蹴躓いたりはせず、無事に玄関へとたどり着くことが出来た。
引き戸を開けて外へと出ると、未だに雨に支配され続けている外の暗い景色の中、背の高い雑草が生い茂っている畑の様子がぼんやりと確認できた。民家の前からはちゃんとした道も伸びていたが、千秋たちの向かう方角とは全く別の方を向いていたので、残念ながら、結局帰りも鬱陶しい雑草たちの密集地の中を通らなければならないのだった。
雨のせいで土が柔らかくなってしまっている畑の中に踏み込んだ途端、足の裏が埋もれていく感覚が身体中に伝わる。片脇に五キロもの錘を抱えている千秋は、ついバランスを崩してしまいそうになったが、圭吾がすぐに身体を支えてくれたおかげで、何とか倒れずには済んだ。
「あまり世話を焼かせるな」
千秋の身体を離してから、ぷいと前を向き直って先に歩きだしてしまう圭吾。
十キロもの肥料を抱えているせいで重心が偏って歩行も困難だろうに、それでも彼はわざわざこちらに気を遣って助けてくれたのだった。なんだろう。この島の中で出合って手を組んだばかりの頃と比べて、彼との距離がだんだんと縮まっているように感じるのは、単なる気のせいなのだろうか。
と、余計なことを考えていると、絡み合った植物に足を取られて、またしても倒れそうになってしまう。これ以上圭吾に迷惑をかけないために、病院に帰り着くまでのしばらくの間、雑念が沸かぬよう気をつけた方が良さそうだった。
「春日」
ふいに前方から呼ばれたので、千秋は歩きながら小声で「なに?」と返事した。
「急にどうしたの?」
「いきなりだが、左手五十メートルほど向こうに誰かが現れたようだ」
鉄パイプを握った右手で前方の草を掻き分けると、レーダーに目を向けたまま立ち止まっている圭吾の姿が見えた。
レーダーには常に注意を払っていたが、拡大表示にしていた時に接近されてしまったため、今の今まで敵の存在に気付けなかった、と振り向いた彼は言う。
「どうするの? もしもこんな時に襲われちゃったら、荷物を放り出して逃げるしかないよ」
「反撃するという手もあるさ。それに、心配しなくてもおそらく大丈夫だ。密集した雑草と闇夜の暗さのせいで、向こうはこちらの存在に気付けていないはず」
たしかに、圭吾の言う通りかもしれない。畑の中は数十センチ先もまともに見られない状態であり、一緒に行動している仲間の姿ですら、声を出し合わなければ簡単には見つけられないのだ。それにもしもの時が訪れてしまったとしても、こっちには剣の達人である圭吾がいる。戦いとなっても簡単にやられたりしないはずだ。仮に相手が銃を持っていたとしても、ここまで視界の悪い場所では、こちらにしっかりと狙いを合わせることも難しいだろう。
「まあ、見つからないよう上手くやり過ごすことが出来れば、それが一番だな」
「今は無事に爆弾の材料を届けられるよう、無駄な戦いは避けるべきだしね」
「そうだ。だから危険が去るまでは極力声と物音を抑えるよう努めるぞ」
千秋は口にチャックを閉めるジェスチャーをしながら頷いた。そして抜き足差し足で再び歩き始める。一歩踏み出すごとにぬかるみがグチャグチャと音を立てるが、そのくらいならよっぽど近寄られない限り、相手の耳に入ってしまうことはないはずだ。
あまり緊張してはいなかった千秋。だが直後、ある一言を耳にしたことによって、額から汗を滲ませることになる。
「マズイな。こいつ、畑の中に入ってきやがった」
レーダーの表示を見ながら圭吾は厳しい表情を浮かべていた。あまり芳しくない状況に焦る彼の心情が、ひしひしと伝わってくるようだった。
「見つかったのかな?」
「それはないはずだ。おそらく偶然だろう」
「それじゃあ今、相手との距離はどれくらいあるの?」
「もう四十メートルもない。ゆっくりとだが、今もこっちへと近づいてきている」
相手との距離が短くなればなるほど、こちらは動きにくくなってしまう。移動の際に生じてしまう微かな音を聞かれてしまう可能性が高まっていくからだ。いくら豪雨がある程度の音はかき消してくれるといっても、こうなってはもはや安心はできない。
「どうする? 向こうが過ぎ去ってくれるのをじっと待っていた方が良いのかな?」
「いや、もう少し静かに進んだほうが良い。今俺達がいる所は、相手の進行方向のど真ん中だ」
なるほど。それならこんな所で止まっているのは危険だ。すぐに圭吾の後に続いてその場から離れることにした。
「どう? 相手はまだこっちに向かってきている?」
自分達に危険が迫るという心配のあまり、千秋はこまめに現状を聞かずにはいられなかった。いつ雑草の隙間から何者かが顔を覗かせるかと思うと、恐ろしくて平静を保ち続けることすら難しくなってしまうのである。
「駄目だ。運悪く相手はまたこちらへと向き直りやがった。まるで位置がばれているみたいだ」
そのとき、圭吾は突然立ち止まって周囲を見回し始めた。そして「しまった」と目を見開いた。
「どうしたの? いったい何があったの?」
千秋は抑えた声で聞くが、圭吾は「そういうことだったのか」と一人で呟き続けている。
「ちょっと、どういうことなのか説明してよ」
「分からないか。自分達の頭上を見てみるんだ」
千秋は訳が分からないまま、言われたとおり目を上へと向けた。そして、全て理解した。
「綿毛!」
「そうだ。俺達が畑の中を進むことによって植物同士が擦れ合い、上手く雨を免れて濡れずに済んでいた綿毛が種子と共に大量に舞い上がる。もちろんこの暗がりの中でそれに気付くのは難しいと思うが、時折雲間から僅かに差し込む月明かりに照らされれば、薄ぼんやりとなら見えてしまうのかもしれない」
「じゃあ、私達は知らず知らずのうちに、舞い上がる綿毛で自分の位置を相手に知らせてしまっていたのかもしれないってこと?」
千秋の顔が青ざめる。するとその時、左手の方からガサガサと草の擦れ合う音が、突然猛スピードで近づいてきた。
「チィッ! やはり気付かれていたか」
圭吾が音のする方へと顔を向けた瞬間、何か先の鋭い物体が足元の土に突き刺さった。敵の襲撃だ。
「誰だか知らんが、俺を狙ってただで済むと思うな!」
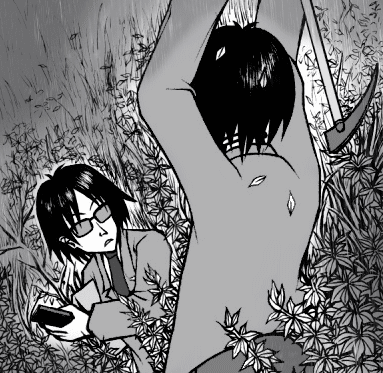
草葉の隙間から、襲撃者が両手で何かを振り上げているのが見える。暗くて顔はよく見えず、相手の正体は分からないままだけど、とにかく圭吾は反撃に出るために二つの大きな袋を急いで下ろし、腰に挿していた妖刀紅月へと手を伸ばした。が、何故かすんなりと鞘から抜けない。運の悪いことに、刀の柄に植物の蔓が複雑に絡み付いていたのだった。
「クソッ! こんなときに」
圭吾の動きが止まった一瞬の隙に、襲撃者は躊躇する様子もなく両手に持っていた武器を一気に振り下ろした。
「危ない!」
千秋が叫ぶ。圭吾は素早く身を捻って、襲い来る一撃をギリギリのところでかわした。刀はまだ鞘から抜けていない。
襲撃者はさらにもう一度攻撃を仕掛けようと、土に深く突き刺さった先の鋭く尖った武器を、またもや振り上げようとしている。ひっひっ、と嗚咽を洩らしながら。
「さ……くら……。さくらぁっ!」
その声には聞き覚えがあった。二年前の火災で自我や感情など、あらゆるものを失ってしまった妹を支え続けてきた優しい兄、白石幹久(男子八番)。驚くべきことに、彼こそが圭吾に襲い掛かった襲撃者の正体なのであった。
【残り 十六人】 |
