全身を覆い包むこのロッカーが地面の上に置かれてからどれくらいの時間が経過しただろうか。
人気のない島内はしんと静まり返っている。
何も見えず、何も聞こえず、何も感じない。こんな五感全てが束縛された状態が長時間続いたならば、本当に気がおかしくなってしまいそうだ。
先ほどまで、トラックに乗せられていたときは、見えないながらもすぐ側に人間の気配があった。しかし今は本当に一人ぼっち。
さらには自分がどこにいるのかも分からないような現状況では、この数分か数十分かとも分からぬ時間が過ぎるのを、ただ待っているというのは、まさに苦行でしかなかった。
狭いロッカーの中でずっと同じ体勢でいたためか、身体の節々がジンジンと痛み始める。
苦しい。早くここから出して!
必死にあがいたのが幸を制し、ようやくキュロットスカートのポケットの中から取り出した携帯電話を、顔の目の前にへと持ってくることができた。
千秋はすかさず折り畳み式の携帯電話本体を開く。すると暗闇の空間内に白く光る液晶画面が鮮明に浮かび上がった。とりあえずこれで時間感覚の狂いだけは解消できそうだ。
液晶画面に表示されている時間は午後十一時五十分。日付が変わるまであとたった十分しかない。
もう深夜か……。いつもならもうすぐで店を閉める時間だ。
ふと平和だった日々を思い出した。
仕事帰りの大人たちを癒すべく、自慢の腕を揮って作った料理を差し出し、その味に満足して喜んでくれる客達の顔を見る。あまり中学生の女の子らしくない日常かもしれないが、千秋にとってはそんな日々を過ごすことが幸せだった。
もちろん、プログラムに巻き込まれさえしなければ、明日からもまた同じように過ごすはずだった。しかし、当たり前のように側にあったその生活も、今や手の届かないところにまで離れてしまった。
もしもこの島から出て家に帰ることができたとしても、そこにはもう大好きだった父もいない。
そして親友だった智香もが死んでしまった。
大切だったものが徐々に消えていく。
考えれば考えるほど、千秋の気分がブルーになっていった。
そんなときだった。今まで無音だった辺りが、少しずつ騒がしくなり始めたのは。
ぽつぽつと水が滴る音が聞こえたかと思うと、それは徐々に激しさを増し始め、最後には大合奏となって千秋の耳に入ってきた。
また降り始めたか……。
身近に感じる雨の気配に対して、千秋は良い印象は抱かなかった。ただでさえジメジメとした気分なのに、これ以上それを後押ししないでほしいというのが本音だった。
『みなさぁん』
湿った空気の中、さらにそれに拍車をかけるがごとく、ネチネチとした男の声が聞こえた。もはやお馴染みとなってしまったこの声の主が誰なのか分からないはずがない。田中だ。
機械を通したこの声はかなり近くから聞こえた。どうやらこのロッカーの中にはスピーカーが仕込まれていたらしい。
『現在時刻は午後十一時五十九分、もうすぐで日付が変わりまぁす。お待たせしましたぁ、それではロッカーの鍵を一斉に解除したいと思いまぁす。悔いの残らぬように頑張って殺し合ってくださいねぇ』
その声が途切れると同時に、すぐ側からガチャリという音がした。その瞬間、時刻はちょうど零時となった。
千秋は恐る恐る扉を押してみた。すると扉は簡単に開いてしまった。
ゲーム開始というわけか……。
窮屈なロッカーの中から外に出ると、目の前には鬱蒼と繁った雑木林が広がっていた。
所狭しと生えている木々は遥か上空へと向かって競争しているかのように伸び、腕のような枝を四方に広げ、葉で天然の屋根を形成している。そのおかげで、降り注ぐ雨の勢いは若干抑えられている。
しかし時間が時間だけに、辺りはとてつもなく暗い。明かりでもなければ移動するのは困難だ。
そういえば。
千秋は何かを思い出し、先ほどまで自分が入っていたロッカーからデイパックを引きずり出した。
ジッパーを下ろして口を広げる。そして中に入っていた物へと手を伸ばす。
取り出したのは懐中電灯。まずはそれのスイッチを入れて明かりを点ける。するとおぼろげにしか見えなかったデイパックの中身がはっきりと確認できるようになった。
五百ミリリットルのペットボトル入りのミネラルウオーター二本。『カロリーブロック』と書かれた固形タイプの栄養調整食品、チョコレート味とフルーツ味が共に二箱ずつ。折り畳まれた会場地図とコンパス。黒インクのボールペンが一本。
そういえば、田中はこのデイパックの中に武器も入っていると言っていたな。
デイパックのさらに奥へと手を突っ込んでみる。するとなにやら硬い物が触れた。
千秋はそれを掴んで外へと引っ張り出してみる。すると、出てきたのは武器なんてものではなく、ただの双眼鏡だった。
まさかこれが武器だとか言うんじゃないでしょうね。
さらにデイパックの中を探ってみる。しかし他に入っていたのはデイパックを膨らませていた詰め物ばかりで、役立ちそうなものは何一つとして見当たらなかった。
田中はこう説明していた。デイパックの中に入っている武器の種類はランダムで、アタリもあればハズレもあると。おそらく千秋が選んだこのデイパックはハズレだったのだろう。
こんな双眼鏡なんかで、どうやって自分の身を守れって言うの。
落胆する千秋。しかし、クラスメートに危害を加えるつもりなど無い自分にとっては、自分の武器がアタリだろうがハズレだろうが関係ないとも考えられる。
こんなことで気を落としていたってしょうがない。進もう。皆で誓い合った集合場所へと。
気を持ち直した千秋は、すぐさま地図で現在地と目的地への方向と距離を割り出そうとした。しかしここは雑木林の中。四方八方無数の木々が生えているだけで、目印になるようなものは何一つ無い。こんな状況で自分がいる場所を割り出すなど出来るはずが無かった。
駄目だ。ここがどこなのか分からない。
千秋は何か目印になるようなものは無いかと思い、懐中電灯で辺りを照らしてみた。すると、思ってもいないものが見つかった。
千秋が入っていたロッカーのすぐ側の地面が奇妙な形に窪んでいる。人工的な力が加わることによって作られた奇妙な形の溝は長く伸びており、その先は雑木林の奥地へと続いていた。これは間違いなく、千秋たちのロッカーを輸送していたトラックが走った後に残った轍だった。
それに気づいた瞬間、千秋の頭の中に一つの案が浮かんだ。
このタイヤの跡に沿って進めば、再会を誓い合った仲間達に出会えるかもしれない。
どっちにしろ自分の居場所が分からない現在、進むべき方向も分からないのだ。それならば、一つの可能性に賭けて進んでみるのも良いだろうと考え、唯一の荷物であるデイパックを持ち上げると、すぐさま轍に沿って歩き始めた。
長く伸びた雑草に何度も足を取られそうになりながら、少しずつ前へと進む。視界が利かぬせいでその移動はかなり困難なものだったが、幸いにも降り始めたばかりの雨が地面をやわらかくするにはまだ至っておらず、デイパックの中身もほとんどが詰め物ばかりだったので、それさえ取り出してしまえば、ほとんど重さを感じなかった。
生い茂った雑草の下に隠れている轍を見失わぬように前に進む。本当ならば懐中電灯で照らしながら進みたいところだが、危険な生徒に見つかっては大変だと思い、これ以上の使用は控えることにした。
もちろんクラスメートのことを疑いたくなどは無かったが、念には念をという言葉がある。ここはできるだけ注意したほうが良いだろう。
暗闇の中で目を凝らし続けていると、徐々に慣れてきたのか、先ほどよりも辺りの様子がはっきりと見えるようになってきていた。
千秋は雨に濡れた髪を拭こうと、ポケットの中からハンカチを取り出そうとした。そのときだった。千秋の前方二十メートルほど前を横切る形で進んでいる光が見えた。どうやら誰かが懐中電灯で辺りを照らしながら移動しているようだ。
とっさにその場に屈む。雨音によって足音がかき消されていたし、暗かったため、向こう側はこちらの存在に気づいてはいないようだ。
あれはいったい誰なんだ?
茂みの影からそっと覗いてみる。すると、相手が握っている懐中電灯の明かりの中で、ぼんやりとその人物の顔が浮かび上がって見えた。徳川良規(男子十三番)だ。暗闇の中にかすかに浮かび上がるその顔は、明らかに恐怖に怯えていた。
相手の正体が分かった瞬間に不安が薄れ、千秋は彼に声をかけようかとも思った。しかし寸前のところで思いとどまる。彼はトラックの中で再会を誓い合ったメンバーではないのだ。何を考えながら行動しているのかも分からない。
はたして彼は危険な人物なのだろうか。それを考えるために千秋は頭の中で彼に関しての情報を引き出そうとした。しかし普段良規と接触する事の少ない千秋の頭の中にはほとんど情報など出てこなかった。唯一思い出したのが、良規はアイドルマニアだったということ。
こんな情報だけでは彼を知ることはできない。
千秋は悩んだ末、良規に声をかけてみることにした。暗闇の中に浮かんだ怯えた表情。それからは殺意などは微塵も感じなかった。むしろ彼の中を支配していたのは恐怖という感情だろう。ならば、こんなところに一人にしておくのはあまりにも可愛そうだ。
千秋は彼も仲間に入れてあげようと考え、良規に声をかけようと立ち上がった。しかしその瞬間だった。
良規の側の茂みの中から何者かの影が飛び出した。そして影が彼の頭に向けて何かを振り下ろすと、良規の手に握られていた懐中電灯が地面へと落ち、辺りが急に暗闇に包まれた。
何が起こった?
千秋は良規のいたほうへと目を凝らしてみる。しかし彼が握っていた懐中電灯が壊れたのか、それとも落ちた衝撃でスイッチがオフになったのか、先ほどまでは見えていた一帯が完全に見えなくなっていた。
ただ、誰かがガンガンと何かを叩く音だけが林の中に響き渡っている。
千秋は状況を把握しようとデイパックの中の懐中電灯へと手を伸ばそうとした。しかしその瞬間に本能が何らかの危険をうったえ始め、その腕の動きを止めてしまった。
事が収まるのをただじっと見ている千秋。
しばらくすると音は静まり、かわりに何者かの荒い息遣いが聞こえてきた。
千秋は言い知れぬ恐怖を覚えた。何が起こっているのか理解はできていなかったが、目線の先で何か恐ろしいことが起こっていたのだと感じた。
自然と足が一歩後ろへと後ずさる。そのとき腐った木の枝でも踏みつけてしまったのだろうか、足元からバキッと何かが割れる音がした。
良規がいた辺りから、何者かがばっとこちらを振り返ったかのような音が聞こえた。
林じゅうに雷光が走った。その一瞬、千秋の目に衝撃的な光景が飛び込んできた。
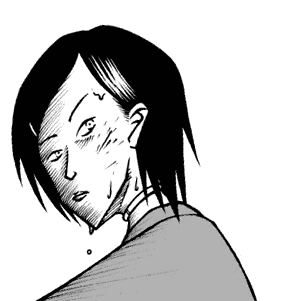
稲光に真っ白く照らされた雑木林の中に立ち、殺意のこもった目でこちらを振り返っていたのは一人の少女。額で左右に分けてピンで止めていた髪から水滴を滴らせ、頬には仕留めた獲物から飛び散った血液が付着している。表情はまるで山姥のごとく次なる獲物の登場に喜んでいるかのように見えた。
山崎和歌子(女子二十二番)。プログラム開始前の分校のグラウンドにて、最初に動き出した三人のうちの一人だった。
そしてその足元で、先ほどまで生きていたはずの良規が、頭をぐちゃぐちゃに潰され、変わり果てた姿となって倒れていた。
稲光が雑木林の中を走り回ってから遅れて数秒後、ゴロゴロと鬼の泣き声のような音が耳に飛び込んできた。
 徳川良規(男子十三番)―――『死亡』 徳川良規(男子十三番)―――『死亡』
【残り 四十二人】
|
