日が地平線の彼方に落ちて早一時間。十月となった今は空が黒く染まるのが早い。
店の出入り口にのれんを掛けようと建物から一歩外に出た瞬間、吹き付けてきた風に身を震わされたので、少女はすばやく用事済ませてそそくさと屋内へと戻った。冬の到来を肌で感じれるようになってきたこの季節、エプロンの隙間から肌に触れようとする冷たい風が忌々しかった。
ガラガラと音を立てる引き戸を締め切り、暖かい厨房へと身を滑り込ませる。
ぐつぐつと煮立つ鍋へと近寄って両手をかざす。途端、温かい湯気が冷たい手をやさしく包み込んでくれた。小さな幸せを感じた。
何気なく壁掛けの丸時計へと顔を向けると、後頭部で一くくりにまとめたポニーテールが元気に揺れた。飲食店で働く彼女にとって、背中まで伸びた髪は邪魔なものでしかなかったのだが、せっかく伸ばした髪を切るのは勿体無いと思っているうちに現在のスタイルに至った。乙女心というもののせいだろう。
時計の短針がもうすぐで六の数字の上に重なる。一日で最も忙しい仕事の時間がやってくるのだ。
平々凡々な中流家庭の街並みの一角で佇む小さな食堂「松乃屋」は、一日の仕事を終えた大人たちにとって、疲れを癒すために訪れるオアシスのような存在だった。
熟年のサラリーマンから、まだ幼さを残す新成人まで、幾人もがその日の疲れを落とすべくここへと立ち寄り、そして暖かい店内で手足を伸ばしてくつろぎながら安い酒をあおるのだ。そして日中無理やり引き締めていた顔の筋肉をだらしなく緩ませる。
どうやら、大人たちは年に一度口に出来るかどうか分からないようなフランス料理のフルコースよりも、懐の夏目漱石を数人手放すだけで手が届くような質素な食事を夢見つつ、その日その日を生き抜いているようだ。
まったくなんて安い夢だろう。
誰もいない店内で、看板娘である少女は一人ため息をついた。
彼女、春日千秋(兵庫県立梅林中等学校三年六組女子三番)は、ようやく温まった両手を鍋から離しながら思った。
彼らの夢が仕事帰りの一杯だというならば、料理を提供するあたしという存在は、幸せを運んでくる女神だといっても過言ではないだろう。実際、酒が美味くなるかどうかは、とっくりの側に付き添う料理の味が決めるといっても良い。脇役が出来損ないなら主役も引き立たない、これ常識。
小学生の頃から父親に料理を叩き込まれた千秋はその腕に自信があった。
初めて来店した客の注文にも速やかに対応して自慢の一品を提供すると、百パーセントの確率で客の顔から笑みが漏れる。
そうやっているうちに、彼らの内の何人かはリピーターとなって再来店してくれるようになる。そして春日家の懐を潤すのに貢献してくれるのだから、本当に感謝しなければならない。
考えを誤った。自分は女神なんて大それた存在などではなかった。
ギブアンドテイクが成り立つおかげで生きていられるこの状態の中で、自分が上の位に立つとは図々しいにも程がある。
人は皆平等。だから皆が生きることが出来るのだろう。
店内でたった一人で暇な時間を過ごしていた千秋は自分でも気づかぬうちに、そんな下らぬ思いを頭に浮かべていた。
時計の長針がもうすぐで十に重なろうとしている。そろそろ客が一人二人と訪れても良い頃だ。
すると、冷え冷えとした外界と暖かい店内を隔てていた木製の引き戸が音を立てながら開き、無精ひげを生やした中年男性が入ってきた。
「いらっしゃい、桂木さん」
ぴしゃりと扉を閉めてこちらを向き直った男に向けて、千秋は元気良く声を掛けた。
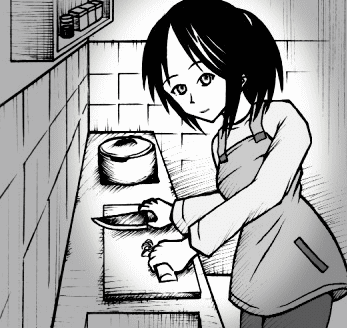
慣れた様子でカウンター席に腰を下ろした客は桂木幸太郎といい、年の頃はおそらく四十前後と思われる。職業に関しては千秋の知るところではないが、よく店を訪れてくれるリピーターさんであるだけに、今では気兼ねなく言葉を交わせるほどの仲となっている。
とても明るく優しい人で、千秋にとってはちょっと年の離れた兄のような存在だった。本当は親子ほどの年の差があるのだけど。
「今日は千秋ちゃん一人かい?」
「うん。今日は天気が崩れるそうだし、客の数もたいしたことないだろうから、全てあたしに任せる、ってお父さんが」
桂木の馴れ馴れしい質問に違和感を感じることもなく、いつものようにさらりと答える。それもそのはず。この店の中では桂木に限らず、リピーターたちの間で彼女は「千秋ちゃん」という愛称で通っているからだ。いまさら気にするほうがおかしい。
「お父さんお疲れなの?」
「うーん、どうだろ。開店前の仕込みは一緒にやってたんだけどねぇ」
しゃべりながら父の姿を思い浮かべていた。
この食堂の店主である千秋の父親。
千秋が物心つくころよりも前に奥さん……千秋にとっての母親だった人を亡くしており、以来男手一つで女の子一人をここまで成長させた偉大なる人だ。
また、千秋にとって父親は料理の先生でもある。
もともとは趣味で始めたという料理への愛着が徐々に増幅していき、気がついたころにはそれが本職になっていたという不思議な経緯をもつ父は、千秋が小学校三年生になった頃に始めて包丁を持たせ、料理を基礎から教え込み、さらには接客の手伝いまでさせた。
今思うと、この店が現在そこそこの売り上げを保てているのは、父が千秋を店に立たせたことにあるのだと思う。
仕事に疲れた大人たちにとって、ここで一杯の酒をあおりながら幼い女の子の相手をすることは何よりもの癒しとなったであろう。そんなこんなでこの店に愛着を抱いた当時の客達は、その腐れ縁のせいで今もここに通いつめることとなっている。
千秋にとっては様々な知識を得ることが出来たわけだし、父は父で思いがけぬ形で利益を上げることができたのだから、まさに一石二鳥だったと言ってよいだろう。
「それにしても、千秋ちゃんまた大人っぽくなってきたんじゃない?」
桂木がまじまじと千秋のほうを見つめて言う。
確かに、彼がこの店に初めて訪れたのは数年前であり、そのときと比べれば、自分は心身共にかなり成長しているだろうし、最近は身長も驚くほどのスピードで伸びているため、彼の目にそう見えていてもなんらおかしくはない。
千秋はえへへと笑って見せた。実際、大人っぽくなったと言われて悪い気もしなかった。
「で、注文はどうします?」
少しの間他愛もないような会話をした後、千秋が思い出したように言うと、桂木は、
「あ、じゃあトンカツ定食頼むよ」
と言った。
「あれ? 今日は飲まないんですか?」
手でグラスを口へと運ぶジェスチャーをすると、桂木は「明日急な仕事が入っちゃってね、あんまり気を抜くわけにもいかないんだ」と言って、残念そうに水を口に含んだ。
「へぇ、大変なんですね。明日は日曜だってのに」
包丁で野菜を刻みながらの会話も既に慣れたもんだ。
「そういう千秋ちゃんこそ、日曜だっていつも店の手伝いをしてるじゃないか。明日だってそうしてるんだろ?」
紳士的で上品な笑顔を浮かべつつ話す桂木。しかし何か見てはいけないものを見てしまったらしく、表情を急に曇らせてしまった。
桂木が見たもの。それは突如悲しみに満ち溢れてしまった千秋の沈んだ表情だった。普段明るく振舞う姿からは想像も出来ないような様子に思えただろう。
「どうしたんだい?」
恐る恐る聞く桂木だったが、千秋は即座にそれに答えることは出来なかった。
言い表しようのないほどの悲しみの塊が突如水面に浮上し、千秋の頭の中を一杯にしてしまったのだ。
少しの間沈黙が続く中、店内に響くのはテンポよくまな板を叩く包丁の音だけだった。
「明日は……店はお父さんだけに任せるつもりです」
ようやく口から出てきた言葉はそれだけだった。しかし桂木は何か納得が出来なかったらしく、再び千秋へと問いかけた。
「明日、何かあるのかい?」
気を利かせて声のトーンを出来るだけ抑えようとしたらしく、彼の口調はとてもなだらかだった。そのためか、今度はだんまりすることなく、すぐに応答することが出来た。しかし、千秋の声は深い悲しみに満たされていた。
「明日は……特別な日なんです……」
包丁の音が止むと同時に、雨が屋根を激しく叩き始めた。
千秋が過去に巻き込まれた壮絶なる事件、兵庫県立松乃中等学校大火災。明日、事件発生から丁度二年を迎える。
|
