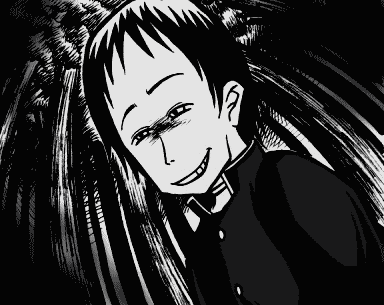130 早紀子の言葉を聞いた雅史は、この時初めて気が付いた。飯峰中に入学して以来、早紀子の声を聞いたのは、これが初めてなのだと。それも仕方の無い話だ。なぜならば、彼女の周りには友人らしき者の姿は存在しておらず、誰かと会話している場面すら見たことがなかったのだから。とはいっても、元々彼女はクラスメート達から拒絶されていたわけではない。クラス内で他者との交流を拒んだのは、他ならぬ早紀子自身だった。 クラスの誰かが彼女に近づこうとも、早紀子は無言のまま何処かへと去ってしまう。そんなことが延々と繰り返されている内に、何時の間にか早紀子は本当に孤立することとなったのだ。 しかし、分からない。なぜ彼女はそこまでして他人との交流を拒んだのだろうか。 雅史が深層心理のレベルで抱いていたその疑問が、ここに来て水面へと浮上した。 不思議に思いながら彼女の様子を窺うと、こちらへと向かれていた相手の視線とぶつかった。 一瞬ビクリとする。相手は罪無き直美を容赦無く殺した死神なのだ。今大人しくしていても、その手に握られている銃が、何時こちらに向けられるとも限らない。緊張感を維持し続けてしまうのは当たり前だろう。 出来ることなら、今この場で直美の仇を討つべく、早紀子を葬り去りたいくらいだったが、自分と相手の戦力差を考えれば、それがどれだけ難しいことであるか思い知らされてしまう。返り討ちにされてしまうのがオチだろう。 しかし、今の彼女は危険に思えなかった。力を失った視線からは殺意が全く感じられず、銃を握るその手もだらりと垂らしたまま、一向に力を込める気配はない。はたして、彼女の身に何が起こったというのだろうか。 威勢を完全に失ってしまった死神を前にして、雅史は呆気に取られていた。 お互いの目を見つめ合ったまま、空白の時が流れた。プログラムに巻き込まれてから、似たような無音時間は何度か経験してきたが、その中でも最も不思議な時間だった。今、彼女は雅史の姿を見て、何を思っているのだろうか。 「……不幸な人生だった」 突如、早紀子が言った。聞き慣れぬその声が再び耳に入ってきたことにより、雅史はまた妙な感覚を覚えた。そして、彼女が言ったその言葉、“不幸な人生”とは、いったい何を意味するのだろうかと疑問に思った。 「私はプログラムが始まってから、もう十人以上ものクラスメート達を殺した。だけど、それには理由があった。名城君、私の話を、聞いてくれる?」 早紀子が再び口を開いた。 雅史の中で、まだ早紀子に対する憎悪は収まってはいなかった。だけど知りたかった。プログラムに巻き込まれたとはいえ、なぜ直美達は殺されなければならなかったのか。そして、早紀子が死神へと変貌してしまった理由。それらがどうしても知りたかった。 無言のまま、こくりと頷く雅史。その姿を確認すると、早紀子はゆっくりとした口調で、ついに衝撃なる告白を開始した。 「……十五年前。県内に住む、ある男女の間に、一人の女の子が生を受けた。まだ幼き二人の間に生まれたばかりの赤ん坊は未熟児として、すぐさま病院の管轄下で、発育促進という偽の表題を隠れ蓑にした“延命措置”を受けることとなった。その女児が現在の私……」 早紀子はまるで独り言のように淡々と話した。話をすることに不慣れな彼女の言葉は、どことなく異質さを感じる。発音も不自然で、言葉のスピードもまちまち。 聞き取りづらいその文字の羅列を読み取るのは、容易なことではなかった。しかし、初めて聞く彼女の言葉に釘付けとなり、雅史はじっとそれを聞く事に徹した。 「通常の幼児と比べ、遥かに未熟な状態で生まれた私の生命は、当時絶望的と思われていたらしい。このまま手を尽くしても、長く生き長らえることはできないだろうと言われていた。だけど、神の悪戯か、私は生き延びることとなった。でも、それを喜んでくれる人は、誰一人いなかった。私の両親だったはずの男女は、幼なき我が子を病院に置き去りにし、何処かに消えてしまったのだから」 それはあまりにも悲しい話だった。しかし、話している早紀子自身は、まるで感情の一部が欠落してしまっているのかのように、全く表情を変えることすらなかった。 彼女の言葉は高低差もほとんど演出されることなく、やはりただ淡々と流れていく。 「引き取り手の無い幼女は、後に孤児として施設に入ることとなった。だけど、そこは孤児達の安息の場ではなく、地獄だった。心無き大人達によって、日々繰り返される虐待。その苦痛にのたうちまわった私は、幼ながらに死を覚悟したほどだった。誰一人文句を言う親がいないのを良いことに、名字も持たぬ幼子達を大人達は好き勝手に弄んだ」 ふと早紀子は上を見上げ、そして天を仰いだ。表情に何一つ動きを見せない彼女だが、内なる感情には変化が現れているのかもしれない。 「そして、私を更なる生き地獄へと突き落とした、運命の日が訪れた。 施設に四十代半ばの男が訪れ、施設の大人達に向かってこう言った。『ここにいる子達の中で、最も醜い子を連れてきてくれ』と。すると施設の大人達は迷うことなく、三才になったばかりの私を差し出した。男は私を見るなり、気に入ったと言って、嫌がる私の手を引いて無理矢理連れ帰った。男の名は吉本弘蔵。現在の私の養父……」 早紀子の衝撃的な告白の数々を聞き、雅史は強いショックを受けていた。生まれながらに愛されることも無く両親に捨てられ、地獄の日々を過ごしてきたということ。そして彼女が吉本家の養子であったことも、これまで知らなかった。何より“醜い子”というレッテルを背負って生きてきた彼女の身になって考えると、それがいかに辛い幼少時代だったかを感じとれ、哀れに思った。 だが、彼女の告白はこれで終わりはしなかった。 「弘蔵は無名の画家だった。私は彼に手を引かれるまま、とある家へと連れて行かれた。それが現在の私の家だった。中に入れるなり、弘蔵は私をアトリエルームの椅子に座らせ、すべての衣服を剥ぎ取った。そしてその私の姿を見つめつつ『素晴らしい、醜い』と喜び勇み、一心不乱にキャンパス上におぞましき悪魔の姿を描いた。弘蔵はなんとも恐ろしげな絵を描く画家で、私はただその絵のモチーフとして、彼の手元に繋ぎ止められる為だけに、吉本の名を受け継いだの。 来る日も来る日も弘蔵が絵を描いている内に、アトリエ内は恐ろしげな悪魔の姿が描かれた無数のキャンパスで溢れた。そして、そのどれもが、私と同じ顔をしていた。 ある時、ついに嫌気がさした私は、弘蔵に反発した。しかし、それがいけなかった。逆上した弘蔵の手によって、木製の椅子で何度も叩き付けられた私は重傷。 両親には捨てられ、施設の大人達からは虐待され、養父には弄ばれ、生まれながら一度たりとも愛情というものを感じたことが無かった私は、この時既にこう思っていた。人間なんて大嫌い」 早紀子はそこで一度話を切った。表情すら変えはしないが、ぼんやりとしたその目の奥では、何やら悲しみが溢れているように見えた。 雅史は想像すらできないほどの、彼女の過酷な幼少期の話にショックを受け、視界に入る風景がガクガクと揺れるのを感じた。 「それから、私が誰かと話をすることなどは無かった。人間不信に陥った私は、とにかく他人との接触を避けて暮した。 六歳になった私は、弘蔵のおぞましき絵のモデルの合間を縫って学校に行くようになるも、やはり他人と交流を持とうとはしなかった。そうやって六年間を無言ですごしている内に、私はいくつかの感情と、言葉を失っていたのかもしれない」 一度間を空け、早紀子はさらに続ける。 「気が付いたときには中学校に入学していた。ここでも、小学校と同じく、他者との交流を持たぬようにすごした。同じクラスの子達が私に近寄ろうとしても、私はとにかくそれを追い払う、あるいは自ら避けた。そうしているうちに、私はやはり校内で孤立した存在となってしまった。だけど、人間嫌いに陥っていた私は孤独を望んでいた。だから、問題など無かったはずだった。私の感情に変化が訪れる、あの日が来るまでは……」 ここにきて早紀子は急に黙り込んでしまった。しかし、すぐに意を決したように表情をきっと引き締め、顔を上げて雅史に視線を向け直した。 「他者との交流を極力拒んでいた私。しかし、ある時にその感情にかすかな変化が現れた。中学ですごすようになった私は、いつの頃からか、ある人物へと目を向けていることが多くなった。始めの頃は、自分の心情にどのような変化が現れているのか、想像すらできなかった。だけど、その人へと視線が向けられている間、胸の鼓動が早まり、体温が上昇していくのを感じている内に、私はある結論に行き着いてしまった。私は、人間に恋をしてしまったのだと。そして、私が恋心を抱いてしまったその人こそ、名城雅史君、あなただったのよ……」 予想だにしていなかったその言葉に、雅史はまたもや言葉を失ってしまった。そんな彼の様子を見て、早紀子は自分自身に呆れてしまったのか、かすかに笑みを浮かべた。 雅史にとって、彼女の笑みを見たこともまた初めてだった。 「不思議な話よね。生涯誰にも愛されたことのなかった私が、一度すら話したことも無い他人への愛情を抱いてしまうだなんて……。だけど、人との交流の術を失ってしまった私は、あなたに話し掛けるどころか、近づくことすらできず、ただ遠くから見ていることだけしかできなかった。それがまた、悲しかった」 そこまで話し、目を伏してしまった早紀子を見て、雅史はとてつもなき悲しみを覚えた。 「そして更なる不幸は訪れた。突如巻き込まれてしまった、今回のプログラム。クラスメート四十六人の内、生還できるのはたったの一人だけ。そんな極限状態へと追いやられた私は、ここである決断を下した。私は自らの生存など望んでいない。ただ、私が生涯愛情を抱いたたった一人の男性の生命、それだけは守り通すのだと」 突如、雅史の脳内に閃光が走った。 「それじゃあ、まさか……、吉本、お前が石川を含めたクラスメート達を、次々に殺していった理由って……」 「そう……。すべては名城君、あなたを優勝させるために行った」 雅史の全身から力が抜けた。 それじゃあ。吉本に殺された皆は……、石川は、俺のせいで……。 「もちろん、私のこの判断は正しいことだっただなんて思ってもいない。石川さんを含め、殺した皆には、本当に悪いことをしたと思っている。ごめんなさい、名城君。辛い思いをさせてしまって。だけど、この悪夢ももうすぐ終わる。もはや生き残っているのはたったの三人。私があと一人殺しさえすれば、あなたはもう自由になれるの。だから、あとほんの少しだけ待って」 早紀子がその言葉を言いきったとたん、すぐ近くで銃声が響いた。そして、雅史の目の前に立っていたはずの早紀子の身体が、突然がくりと崩れた。 雅史は倒れた早紀子の身体の向こう側に立つ、一人の男子生徒の存在に気が付いた。高らかと銃を掲げ、喜ばしげに「やった」と騒いでいるのは、紛れもなく生き残り三名のうちの一人、中村信太郎(男子15番)だった。
【残り 3人】 トップへ戻る BRトップへ戻る 129へ戻る 131へ進む |