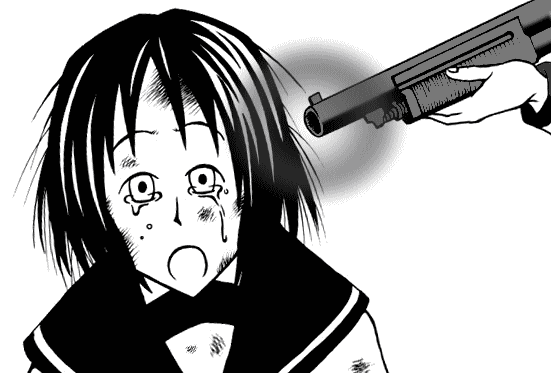127 死んだ……。剣崎が死んだ……。 剣崎大樹が死亡してから、既に数分の時間が経過していたが、雅史はいまだに、その事実を受け入れる事が出来なかった。 誰よりも強く、頼り甲斐があり、そのくせ優しい一面を持ち合わせていた彼に対して、雅史は何時の間にか信頼を抱いていた。しかし、その彼は先ほどから一度も動こうとはしない。右胸部に大きく開いた弾痕からは、勢いを緩めることなく血が流れ出し、湿った土を赤く濁らせ続けている。 右胸部の弾痕。これが大樹を死に至らせた事は明らかであった。そして、この弾痕を作り出した人物は紛れも無く、大樹の側で地面に両手両足をつけながら、動かぬその姿を見下ろし続けている男、名城雅史。 殺した……。俺が……剣崎を殺した……。 雅史は地面から手を離し、その両手を自らの顔の前へと移動させ、じっと見た。一見するといつもと変わらぬ我が手のひら。しかし、生まれてこのかた十五年間見続けてきたそれは、つい先ほど血に染まってしまった。そう思うと、長い間共に過ごしてきた我が身の一部であろうとも、たいへん汚らわしく感じられた。 ――強く生きろ。 大樹が死に際に放った最後の言葉がよぎった。言葉そのものは短いが、大いなる意味の込められたそれは、いかにも大樹らしい台詞に思える。しかし、自己嫌悪のどん底へと突き落とされた雅史には、その言葉に答えられそうになかった。 蒸発したかのように身体中の力が何処かへと消え去り、頭の中ではグレーのもやもやが蠢くばかりで、思考回路は全く正常に作動していない。まさに、気力体力どちらもが尽きた状態で、強さの欠片すら見る影もない。 無理だよ、剣崎……。こんな俺が強く生きるだなんて……。 自分の無力さを恨んだ。 「私の……せいだ……」 雅史の側で声がした。直美だった。 「私が剣崎君のことも考えずに、撃ってなんて言ったから……」 眼鏡をなくして何も見えていないであろう彼女は、その濁った目にうっすらと涙を浮かべ、後悔しているようだった。 「石川さんのせいじゃないよ。俺がこの手で剣崎を……」 「名城君のせいじゃない! 私が自分勝手に言ったせいで、剣崎君を死なせてしまった。それも、名城君に罪を着せて……」 雅史の言葉を押しのけて直美がそう言った。 悲しみでいっぱいの眼差しをこちらに向ける直美の姿を見て、雅史は彼女がどれだけ苦しみ、そして後悔しているのかを感じ取った。おそらく雅史と同じくらい、いや、それ以上の苦しみに襲われているようにも見える。 「確かに私は須王を許せなかった。大切な友人たちが次々と死んでいき、そんな状況に耐え切れなくなっていた私に追い討ちをかけるかのように、忍の生命までもを消し去ったあの男を死なせたかった。だから、私はそれ以外には何も考えずに、名城君に言ってしまった。あの男を殺して、と……」 雅史は何も言い返せなかった。大樹を人質にした須王と対峙したあの状況では、確かに直美のその一言は、雅史の背中を後押しする力となってしまったのだから。 「その結果、須王をこの世から消し去る事は出来た。だけど、それにはあまりにも犠牲が大きすぎた。剣崎君は須王と共に死んでしまい、名城君はその手を血に染めてしまった。自分の両手は潔白なままなのに……」 「石川……」 雅史は彼女に何か言ってやりたかったが、上手い言葉が思いつかず、唾を飲み込む事しか出来なかった。 うつむき加減になっていた直美が、ゆっくりと顔を上げた。 「ほんと……卑怯だよね、私……」 直美の目に浮かんでいた涙が溢れ出した。ダムが崩壊したかのように、一度流れ出したそれは、もう流れを止めることはなかった。 ほんの少しの間の沈黙。時が止まってしまったかのように、あるいは永遠の無音世界に迷い込んでしまったかのようにすら思った。しかし、いつまでもそんなところで戸惑い迷い続ける訳にはいかない。今、この弱々しき少女を守ってやれるのは、自分以外にはいないのだ。 雅史はもう一度あの言葉を思い出した。 ――強く生きろ。 そう、強くならなければ、自らの生命は勿論、大切な仲間を守り通す事は出来ない。ならば、今ここで崩れ去る訳にはいかない。彼女を守る為にも、自分は今ここで変わらなくてはならないのだ。 雅史は拳を強く握り締めた。 「石川……、お前は自らの行いに後悔しているようだが、俺は、間違っていたとは思わない……」 搾り出したような声。上手い言葉を見つけ出す事が出来ず、自然と弱々しい口調になってしまったようだった。しかし、それでも直美を驚かせるには十分だったようだ。 突然口を開いた雅史の顔を、彼女はじっと見つめてくる。 「たしかに、石川さんの発言は事態に何らかの影響をもたらしたかもしれない。だけど、もしもあの時、石川さんが何もしなかったら、事態はどんな方向へ向かっていたか、分かったものじゃない。全て想像に過ぎないけど、もし石川さんが何も言わなかったならば、今頃、俺は須王に銃を渡してしまい、そして剣崎ばかりか、俺や石川さんの命までもが奪われていたかもしれない。だとすると、石川さんは自らの命を防衛するのみでなく、俺の命までもを救ってくれたということになる。ならば、恐怖に負けて踏み止まろうとしていた俺の背中を押してくれた石川さんに、むしろ感謝したい。 それに、石川さんは何も自分の命を守る為に、あんな発言をしたわけじゃない。全ては親友の仇を討つためだろう。自ら悪人を演じてまで、親友のことを想う……。俺はそんな石川さんが結構好きだ」 話している間に、自らの顔が紅潮していくのを感じていた。くさい単語が列を成すのを思い浮かべると、我ながらなんて恥ずかしい事を言っているのだと思い、体温がだんだんと上昇していった。 雅史の話を呆然と聞いていた直美だったが、恥じらいつつ紅くなっている雅史を見て、つい笑みをもらしてしまった。 「ほんとに、名城君って良い人だね。自己嫌悪に陥っていくばかりの私とは違い、名城君は、自分だって苦しんでいるのに、それでも他人をも助けようとする。昔からそうだよね。昔から……。」 昔から? 雅史は直美の言葉に引っ掛かりを感じた。彼女が最後に言った『昔』に、はたして自分の身に何かが起こっただろうか? いくら懸命に考えてみても、それらしき記憶は浮かんでこなかった。 直美は袖で涙をぬぐい、再び雅史の顔を見つめた。 「ダメだ。いくら涙をぬぐっても、やっぱり眼鏡がなかったらよく見えない……。名城君の、今の顔が見たいのに……。ねぇ、もっと近づいて見ていい?」 突如投げかけられたその言葉に、雅史はついドギマギしてしまった。 「えっ? ど、どういうことだ?」 どう答えれば良いのか分からず、あたふたするばかりの雅史の返事を待つことなく、直美は行動を開始した。 雅史の瞳に映る直美の姿が、徐々に大きくなっていく。泥にまみれ、傷だらけとなったその顔は、たいへんみすぼらしく思えた。しかし、彼女の純粋さの象徴ともいえる澄んだ瞳は、今もまだ彼の瞳の中で美しく輝き続けている。そして、その瞳は何かを訴えかけるように、対面する瞳と視線を交わす。 「綺麗な目……。やっぱりやさしい顔してるよね、名城君は……」 雅史を見つめたまましばらく黙り込んでいた直美が、ゆっくりと口を開き、そう言った。 見つめあう二人の視線、その間の距離たった数センチ。お互いの息を肌に感じる事すら出来るその状態に、雅史は緊張した。 突如、雅史の視界から直美の瞳の姿が消えた。かわりに唇に何か柔らかいものが触れたのに気づく。 ほんの一瞬の事であった。雅史が瞬きすると、直美の瞳は先ほどと同じ位置に戻っていた。しかし、じっと雅史から視線を外そうとしないその瞳には、数秒前よりも更に強い意思が込められているように感じた。 今、雅史の唇に触れたものは何だったのだろうか? 今の出来事は幻ではないのだろうか? 自らの胸の鼓動が急速に早まっているのが感じられた。まだ唇に残る感触の余韻が、彼の頭の中を真っ白にさせた。 「私、ずっと言っておきたい事があった……」 直美が口を開いた。それと同時に、雅史の視界に、直美の瞳とは違う別の物の姿が飛び込んできた。 あれは……。 その正体を把握した瞬間、雅史は言い知れぬほどの緊張を覚えた。しかし、直美はまだその姿に気がついていない。 「実は……私……」 直美の言葉は耳に入らなかった。雅史の視線は直美の顔には向かっておらず、意識は全く別の物に引き寄せられていたのだから。 直美のこめかみへと近づき、妖しく黒光りする銃身。その先端からは恐ろしいほどの殺意が放たれているように感じた。 「逃げろぉっ! 石川ぁ!」 大声で叫ぶが、直美は眉を動かす事すらなかった。そして、じんわりと目を潤わせながら、意を決したように言った。
「私、実は名城君のことが――!」 【残り 4人】 トップへ戻る BRトップへ戻る 126へ戻る 128へ進む |